内容説明
堀、土塁、切岸、竪堀、馬出、枡形虎口(ますがたこぐち)、横矢掛り(よこやがかり)、櫓台(やぐらだい)、曲輪(くるわ)、そして天守……。城が備える様々なパーツ(部位)に注目し、その発達と役割・機能を考えることで城の本質に迫る。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
62
城見物は天守や石垣でおしまいなのが大半だが、それだけでない城郭を構成する細かいパーツの数々を教えてくれる。畝状竪堀群や堀切、障子堀、切岸、腰曲輪などの存在は本書で初めて知った。何より城とは戦国時代に軍事施設として発展し、経験や地形を生かし防御の工夫が凝らされてきた事実を再認識させてくれる。今日の日本人がイメージする城主の居宅や権力の象徴としての城は、織豊から江戸期にかけて城の形が進化した結果なのだ。実用品であり兵器そのものである城の実像を、自国の歴史でありながら理解していない人びとへの苛立ちが垣間見えた。2021/04/22
スー
21
77堀や曲輪や虎口などをパーツごとに詳しく説明されているのでとても分かりやすかったです。地形をどう活かすかや経験から城がどういう風に進化していったかという過程も楽しめました。2021/06/17
ようはん
17
曲輪や虎口など城郭を調べると登場する用語に関して細かく解説しており新たに知る事も多かった。いかにして城を攻める敵兵の動きを制限するか、敵兵に対してどれだけ複数方面から攻撃出来る構造を作れるかが重要であると感じる。2023/11/07
YONDA
15
城(土の城がメイン)のパーツについて非常に分かりやすく説明されている。コロナのため城巡りになかなか行けないので、復習にもなり予習にもなりました。最終章の領主別編成から兵種別編成への変遷において、本郷先生が意を唱えていたとは初耳。2021/06/06
オルレアンの聖たぬき
4
改めて読み直すと発見も多い。『城』とはあくまでも戦闘のための施設で、そこに立てこもるのは戦闘のために集まる人々。そこに居を構えて生活していたのは、それほど多くはないのだとわかる。2024/11/25
-
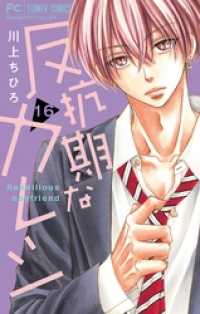
- 電子書籍
- 反抗期なカレシ【マイクロ】(16) フ…
-

- 電子書籍
- ビデオグラファーのための音声収録&整音…
-

- 電子書籍
- ニューモデル速報 統括シリーズ 202…
-
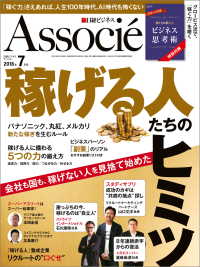
- 電子書籍
- 日経ビジネスアソシエ 2018年7月号
-

- 電子書籍
- マギクラフト・マイスター 4 MFブッ…




