内容説明
記紀と『風土記』の記述の相違
神話に隠された秘密を明かす
記紀神話の3分の1以上を占める出雲神話。しかしその出典たる『出雲国風土記』には、記紀とは異なる舞台、神々の美しく雄大な詩が綴られていた。それらを抹殺し、出雲国を強大な国であるかのように仕立てあげた大和朝廷の策略とは、どのようなものだったのか。国引き説話や大神の麗しい物語が、支配者によってねじまげられ、被支配者たちに受け入れられていく過程を解き明かす。
出雲の弱小国がどういう理由で神代巻の3分の1も占めるとともに、それに基づいて起こった錯覚によって、1000年もの長い間、大和朝廷に対立する強大な出雲国を、われわれに想像させてきたのであろうか。まず読者のすべての方に申したいが、これまでの出雲観のすべてを完全に拭い去って、白紙の立場で新しく出雲を見直す心がまえを持っていただきたいと思う。――<本書より>
目次
第1部 出雲国造をめぐって
1 出雲族の発祥地
2 国造出雲臣
3 郡領としての出雲臣
4 氏族構成から見た出雲
5 国造系譜の疑問
第2部 出雲神話誕生の秘密
1 出雲神話の担い手
2 杵築大社の創建者
3 出雲神話誕生の経緯
第3部 出雲神話の分析
1 出雲の大神たち
2 大蛇退治の説話の源流
3 須佐之男命の出自
4 大国主神の説話の分析
5 三輪・賀茂氏との関係
6 黄泉国の説話
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
うえ
4
1966年刊の文庫版。「『古事記』や『日本書紀』に出雲神話として載せられた内容は、出雲国造にとっては予想もしなかった驚きであったと思われる。往古から出雲族の大神であった熊野大神の名もみえないし、本貫である意宇川流域に因んだ説話も記されていない。…開発の神としてまつられた大穴持命(大地主命)が、『古事記』では翻訳されて大国主神と呼ばれ、国譲り説話の主人公となっていたのである。これに対し、須佐之男命は神門川の上流、須佐の地の説話にみる神ではあったが、大蛇退治のこの説話は舞台を肥河に変えられていた。」2025/02/19
Ryosuke
2
竹2023/09/03
茅野
2
面白くて一気読み。出雲神話は誰により、如何にして創作されたのか、という心躍る内容。但し、前半部は中世日本の統治や出雲の地理についてなどの前提知識を必要とする。2021/06/05
kaz
2
記紀神話における出雲神話の分量は3分の1にもなり、数々の神も登場する出雲。このことから古代においては出雲が絶大な勢力を誇る文明を持っていたと見る向きがあるが、この本ではそれは専ら天皇を中心とした集権国家の権威をつけるために「出雲のような強大な国を下した大和」という文脈のために作られたイメージであるとする。(少年漫画で主人公に強い敵を倒させる展開、的な)また出雲神話は土地にもともと伝わっていた様々な神話をコラージュして作られたあとがみられるとし、古事記編集者の創作の部分も多いとする。かなり説得力があった。2019/07/26
satoshi
2
梅原猛『葬られた王朝』に続いて読んだ。『葬られた王朝』は,著者はかつて出雲神話は大和で起こったことを出雲に移し替えたフィクションだと書いたけれど,それは誤りであって,やはりスサノオ,オオクニヌシの出雲王朝があったのだという内容。一方この『出雲神話の誕生』は,記紀の国譲り神話などからかつて出雲族の大国が存在したかのように思われているが,それは天皇中心の中央集権確立のためにつくられた皇室中心主義的神話のいわば副産物にすぎないと見る。主張が正反対でおもしろかった。個人的には後者の方が説得力あり。。2010/08/06
-
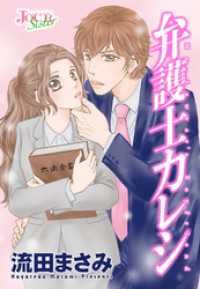
- 電子書籍
- 弁護士カレシ 分冊版 113 ジュール…
-

- 電子書籍
- 0歳児スタートダッシュ物語 【フルカラ…
-

- 電子書籍
- 隣のステラ ベツフレプチ(23)
-

- 電子書籍
- 僕の婚約者の話【タテスク】 第35話 …
-
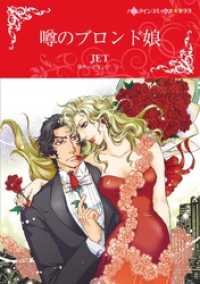
- 電子書籍
- 噂のブロンド娘【分冊】 9巻 ハーレク…




