内容説明
二者の協同的な狩猟採集から始まった相利共生的な相互依存関係は、「わたしたち」という共同主体へのコミットメント、文化集団との一体化へと発展し、道徳的アイデンティティの形成・維持に繋がった。比較心理学実験の成果と哲学的議論を融合させ、霊長類との共通祖先から現生ヒトにいたる道徳性の進化プロセスを体系的に論じる。
目次
序 文
第一章 相互依存仮説
第二章 協力の進化
協力の基盤
大型類人猿の協力
血縁・友情に基づく向社会性
第三章 二人称の道徳性
協同と援助
共同志向性
二人称の主体
共同コミットメント
「べき」の起源
第四章 「客観的」道徳性
文化と忠誠
集合志向性
文化的主体
道徳的自己統制
善悪の起源
コーダ:エデンの園の後
第五章 協力+(プラス)としてのヒト道徳性
道徳性の進化に関するさまざまな理論
共有志向性と道徳性
個体発生の役割
結 論
訳者解説
注
参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
roughfractus02
6
実証科学をベースに本書を読むと、データの乏しいコミュニケーションの人類史を主題とした著者の主張は論拠が弱く見えるようだ。が、本書は少ないデータながら仮説を修正し演繹する過程として読める。600万年前の類人猿が20万年前にの現生人類の共同志向に移る過程に、200万年前の環境圧力下にある初期人類を仮説し、自己(1)→他者(3)の過程の中に相手(2)を組み込んで共同狩猟採集の場面を思考実験することは、帰納的な実証には程遠い。が、本書はそのような思考実験を要する人類史のミッシングリンクの存在を示す点で興味深い。2021/12/29
marukuso
3
人は他者を意識することで「わたしたち」という感覚を身につけ,モノや言葉,概念を共有したりできるようになった。そしてその中で共通の目的をどう協力して達成するか,どういった規範が必要かが進化してきたのであろう。道徳性は2段階で個人のレベル,コミュニティのレベルで進化してきた。多くの実験結果から描く認知の進化論でもあるように感じた。2022/07/24
mim42
3
道徳性の進化に関する仮説。個体から二個体、二個体から集団へという二段階進化仮説。同情が二個体間では配慮となり、集団への忠誠となること、個人志向→共同志向→集団志向という方向性。これらの仮説がどれほどの物理的証拠に根拠付けられているのかは私には不明だったが、少なくとも、人間の子供や幼児、類人猿を使った実験は数多く行われているようだ。これまでの遺伝子と文化の共進化や道徳心理学、進化倫理学については、批判或いは説明可能的観点での物足りなさを指摘されている。本論を脳進化や初期の言語進化と併置したい。2021/03/15
-

- 電子書籍
- 裏バイト:逃亡禁止【単話】(58) 裏…
-

- 電子書籍
- ふりだしから始まる覚醒者【タテヨミ】第…
-
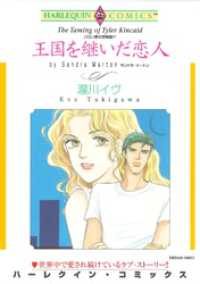
- 電子書籍
- 王国を継いだ恋人〈バロン家の恋物語Ⅳ〉…
-

- 電子書籍
- 週刊ビッグコミックスピリッツ 2021…
-

- 電子書籍
- 【分冊版】転生しまして、現在は侍女でご…




