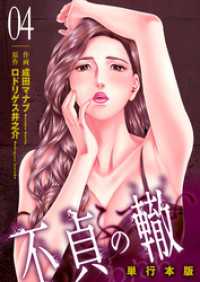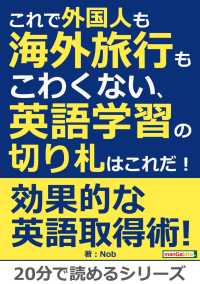内容説明
維新から間もない激動の時代に書かれた『文明論之概略』は、「人類の目指すべき最大の目的」としての文明の姿を鮮やかに描くと同時に、当時の日本が置かれた状況を冷徹に認識して、「自国の独立」の重要性を痛切に説く。物事の本質を見抜き、時代を的確に捉える知性。巧みな例示とリズミカルな文体。福澤諭吉の最高傑作にして近代日本を代表する重要著作が、いま現代語でよみがえる!
目次
はじめに
第一章 まず、議論の基準を定めよ
「議論の本位」とは何か
なぜ議論がかみ合わないのか
深い議論と浅い議論
異端妄説こそが世の中を進歩させる
第二章 なぜ西洋文明を目指すのか
「文明」には段階がある
西洋文明も究極の文明ではない
文明には「事物」と「精神」がある
精神を求めることの難しさ
腕力から智力へ
日本文明と中国文明のちがい
「国体」とは何か
政治の本筋
血統
皇統と国体、どちらが重要か
「惑溺」を払うべし
古さを誇ることの愚かしさ
第三章 文明の本質
文明とは何か
文明以前の段階
自分勝手な基準を文明に押し付けてはならない
「本」と「末」を正しく見分けよ
君主制と合衆政治
政治制度は手段である
第四章 一国の智徳
国の智徳とは何か
人間の心はさまざまに移り変わる
「統計」という方法
原因には「近因」と「遠因」がある
「時勢」を考える必要性
孔子は時勢を知らなかった
楠木正成は時勢に敗れた
時勢を作るもの
時勢論は運命論ではない
第五章 続・一国の智徳
智力の強弱
明治維新が成功した本当の理由
攘夷論は近因、智力が遠因
智力は数では決まらない
スパイほど愚かな手段はない
人が集まれば議論も変わる
習慣の威力
第六章 智と徳の違い
四種類の智と徳
わが国の「徳」は受け身の徳
世の中が進めば私徳では足りない
徳を否定しているわけではない
徳は「内」、智恵は「外」
徳には進歩がない
徳は試験できない
智恵は試験できる
徳の進退、智恵の進退
道徳だけでは不十分
智恵の力を発揮させよ
宗教の広まり方と優劣とは別問題
日本に徳は不足していない
智恵こそが優先課題
宗教は時代で変化する
善人がなす悪、悪人がなす善
智徳論のまとめ
第七章 智徳を行なうべき時代と場所
時代と場所を判断することの困難
古代の人民の扱い
智力の発達
私徳から公徳へ
徳の場所は限定されている
規則と徳は相容れない
規則の効能
第八章 西洋文明の歴史
西洋文明の特徴
ローマ帝国と中世暗黒時代
教会の権力
民主制の要素
君主制の要素
ゲルマン民族による自由独立の気風
封建制の時代
教会の最盛期
市民の台頭
十字軍
中央集権化
宗教改革
人民と王権
第九章 日本文明の歴史
権力の偏重
治者と被治者
政府は変わっても国のあり方は変わらない
人民は政治にかかわらない
人民の地位が上昇しない
独立した宗教がない
独立した学問がない
儒教の限界
武士にも独立の気概なし
権力争いが政治のすべて
第二歩を考えて初歩を踏み出せ
権力偏重は文明の進歩を阻害する
経済の二大原則
日本の税制
蓄財と消費が別々になる害
経済活動に必要な習慣
第十章 自国の独立
文明論の課題とは
日本を支配していた風習
いま休息している余裕はあるのか
国体論の無理
キリスト教の無理
「外国交際」こそが最重要の問題である
品行に与える影響
切実な危機感を持つべし
世界の状況を知るべし
「天地の公道」よりも「報国心」
軍備だけではどうにもならない
「国の独立」こそが目的である
目的と手段
訳者解説
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
藤月はな(灯れ松明の火)
おさむ
姉勤
道楽モン
アミアンの和約