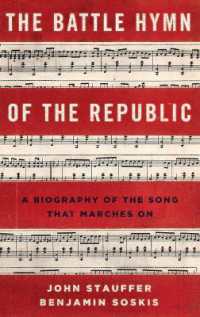内容説明
近年、憲法改正が、これまでになくリアルな問題として論じられている。しかしながら、その議論を行ううえでの素地、日本国憲法の三大原則「国民主権」「基本的人権」「平和主義」はきちんと理解されているのだろうか?この三大原則を多くの日本人はなんの疑問も持たず、それぞれを「皆で話し合って決めましょう」「人としての権利は大事にしましょう」「もう争いごとはやめましょう」というように理解している。しかしながら、その理解は正しいのか?
中学校の「公民」の教科書を検討しつつ、長谷川・倉山両氏は以下のように指摘する。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
イカカイガカ
11
「国民主権」「基本的人権」が生み出された歴史的背景のそら恐ろしさが分かる本。ヨーロッパでは、それらの「フィクション」をどうしても発明しなければならない理由があったということだ。日本は古事記以来、そんなものを全く必要としない国柄だったわけで、歴史的に見ても主権の思想はいらないものなのである。日本国憲法を70年にもわたり押し頂いているバカバカしさ。この悔しさをどこにぶつけるべきなのか。2014/02/19
Y田
10
国民主権、基本的人権、平和主義について、これらは無条件に良いものというイメージがあるが「無条件」にとは必ずしも言えない事を、この概念が成立する歴史を元に解説する。主権は多数派の決定によって支配者を殺していいという革命の思想からきている事、人権は弱肉強食より酷い無秩序状態を自然と考える人工的なものである事など、一つ一つの事項としては知っている事なのだが、事柄を繋げ直して意味を考えるきっかけに出来たと思う。当然だが民主主義には弱点はある。考えて行動する人でありたい。2019/07/13
ミナ
10
今まで表面的だったなぁとつくづく思わされた。そもそものところを押さえないで議論したって良い案なんて出てこない。きちんとした有識者から学び、議論を深め改正案を出して欲しいなぁ。そして、「国民主権」は何が起ころうとも国民のせいになるのだから、せめてちゃんとした人を代表とできるよう教育がしっかりしないといけない。2018/06/17
みじんこ
9
日本国憲法で語られる三大原則(特に基本的人権の尊重)の概念は欧米ではいかに誕生し、日本ではいかに矛盾したものになっているかが語られる。確かに拉致被害者の人権が損なわれており、彼らの人権を回復できていない時点で現実に全く合致していないことは明らかである。また、前述した欧米的価値観による国民主権等の概念は、日本のそれまでの歴史に照らし合わせれば元から不要である、というのも初めて気づかされた。本書は所々哲学的でもあり、頭の中で整理して読み進めねばならなかったが、短い本ながらも内容がしっかり詰め込まれている。2015/02/03
Sally
9
日本はそもそも「人権」という言葉の、その「権利」という言葉がしゃしゃり出てくる余地のない国家体制。それなのに日本国憲法は人権のハイパーインフレに。確かにみんなが欧米のような義務のない権利を主張したら混乱します。そして「国民主権」、これは特に怖く、誰にも責任がないということ。そしてヨーロッパ生まれのそれは、「支配者を妥当すべし」というイデオロギーが常に貼りついている。責任者がはっきりしている明治憲法の方がずっとまともな憲法だと考えさせられた。2014/04/23
-
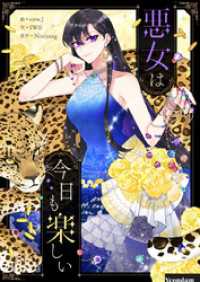
- 電子書籍
- 悪女は今日も楽しい【タテヨミ】第79話…