内容説明
おとなになるまで診断もアセスメントもされなかった自閉スペクトラム症の人たちは、何を知る必要があるのか? そしてどのようなサポートを必要としているのか? 自閉スペクトラム症のアセスメントや診断プロセスのわかりやすい解説、コミュニケーションや感覚に関する自閉特性との上手な付き合い方、自閉スペクトラム症をもつ人たちの年齢別ケースレポート、そして当事者の声を通じて、当事者と家族の知りたい気持ちにしっかり応えていく。どのように自分と家族の「自閉スペクトラム症」を理解していけばよいのかを伝える自己理解ガイド。本田秀夫推薦(信州大学教授・精神科医)!
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
優希
49
自閉症当事者としては興味深かったです。自分の障害がどのようなものか知ることができました。2021/11/10
ひろか
12
非常にあったかい気持ちになる。文体は優しく、当事者、家族が自己理解できることを願っている本。2020/05/24
hiyu
8
事例を中心に自閉症スペクトラムについて述べてある。平易な文章で非常に分かりやすいものでもある。第5章の当事者の声が印象的であった。所々の参考文献も参考になった。2020/03/05
ぽんてゃ
7
受け身的で、自分から人に関わらない 社交をしたがらず、また興味もない 優先順位をつけられないため、生活の中では自分にとってしっくりくることが最優先になる、そのために生活ですべきことが一切できない。など、人のプライベートに興味がなく、雑談は付き合えるけど意味を見出せないとか自分は冷たいのかと思ってたけど、特性的な感じで、自己否定するまで欠陥認定しなくても良いんだと思えた。こんなの無自覚で生きるのハードすぎるよね🥹私も自分の感情に鈍感なところがある。何が問題かわからないとかもある。自閉の方が強いかも。2023/08/06
luckyair
3
実践と理論がバランスよく記されており良書の部類。理屈一辺倒でも情緒中心でもなく、当事者の苦しみが特性の描写とともに記載されている。出版年を見ると2019年とあったが、変化の速いこの領域の本にしては2023年現在でも十分に読むに堪える内容と感じた。総じて、人生の早い段階で特性に気付き、適切な支援を受けたり合わない環境を避けることと「あるべき」普通からの脱却(SSTなどにみられる"努力すれば改善する"圧が翻って努力不足とみなされる懸念)は大事と思った。「苦手こそ習い事で克服させようとしない」にも納得。★★★☆2023/11/06
-
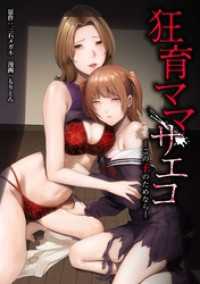
- 電子書籍
- 狂育ママ・サエコ─この子のためなら─第…
-

- 電子書籍
- 固有値計算と特異値計算
-
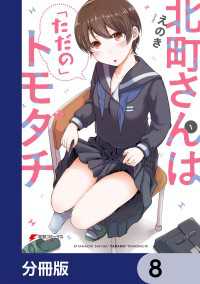
- 電子書籍
- 北町さんは「ただの」トモダチ【分冊版】…
-
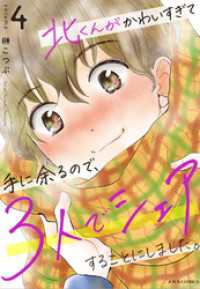
- 電子書籍
- 北くんがかわいすぎて手に余るので、3人…
-
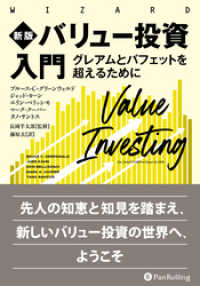
- 電子書籍
- 新版 バリュー投資入門 ──グレアムと…




