- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
ヨーロッパはいかに二つの陣営に分断され、ベルリンの壁はどう築かれたか。ベルリンの壁崩壊から、なぜ分断が一挙に統合へと向かったのか。ドイツ問題を軸に、東西間の対立と緊張緩和の過程を描き、冷戦の国際政治力学を浮き彫りにする。さらには、軍事的・経済的な対立と緊張緩和が交錯するドラマが活写される。ブレグジットで欧州統合が大きな曲がり角を迎え、世界が再び地域主義の様相を呈しているいまこそ参照すべき、最新研究に基づく現代ヨーロッパ国際政治史入門。
目次
はじめに
第一章 ヨーロッパの分断──一九四五~四九年
1 鉄のカーテン
ソ連の戦後構想
チャーチルのパーセンテージ協定
ポーランド問題
ドイツの戦後処理
ドゴールのフランス
ベヴィンのイギリス
2 ドイツをめぐる対立
フランスとソ連の対独政策
イギリスの対独政策
アメリカの対独政策
バイゾーン
3 分断ヨーロッパの制度化
トルーマン・ドクトリンか共産党の排除か
マーシャル・プラン
欧州経済協力委員会とコミンフォルム
4 東西ドイツの誕生
ソ連のドイツ占領政策
ロンドン勧告と通貨改革
ベルリン封鎖と大空輸作戦
東西ドイツの誕生
ドイツ問題
【コラム1】チトーの冷戦──ユーゴスラヴィアの独自外交
第二章 冷戦の軍事化と経済的分断──一九四九~五三年
1 第三勢力からNATOの創設へ
第三勢力構想
チェコスロヴァキア政変
北大西洋条約へ
2 ヨーロッパの経済的分断
ソ連による経済的東欧支配
西側の経済秩序と経済冷戦
西ヨーロッパの統合
3 ドイツ再軍備問題
ソ連の核実験
朝鮮戦争の影響
プレヴァン・プラン
4 東側陣営の対抗
大軍拡とプラハ宣言
スターリン・ノート
二つの陣営
【コラム2】北欧の冷戦──NATOか中立か
第三章 二つのドイツと二つの同盟──一九五三~五五年
1 チャーチルの冷戦
チャーチルの首脳外交提案
禁輸の緩和
ニュールックと核依存
2 ドイツと欧州安全保障をめぐる対立
東ベルリン暴動
アデナウアーと外相会議の提案
ソ連の対案
ベルリン外相会議
3 EDCの挫折、ワルシャワ条約機構の誕生
ソ連のNATO加盟提案
EDCの挫折
ワルシャワ条約機構の誕生
4 二つのドイツとハルシュタイン・ドクトリン
ジュネーヴ四巨頭会議
ソ連と二つのドイツ政策
ハルシュタイン・ドクトリン
デタントの三つの領域
【コラム3】ヨーロッパ・デタントの傑作──オーストリアとハンガリー
第四章 東西両陣営の動揺──一九五六~五八年
1 ポーランドとハンガリーの一九五六年
ラジオ・フリー・ヨーロッパ
スターリン批判とポーランドの一〇月
ハンガリー革命
2 西ドイツの核武装問題
英仏共同三段階軍縮提案
ラドフォード・プランと西ドイツの反応
ユーラトム
スエズ戦争
3 核共有・非核地帯・反核運動
アメリカと核共有
仏・伊・西独協力の終焉
ラパツキ・プラン
反核運動
4 経済・文化交流デタント
英ソ・仏ソ首脳会談
西独・ソ連通商協定
動き始めた経済文化交流デタント
【コラム4】ハルシュタイン・ドクトリンの発動──ユーゴスラヴィアと西ドイツ
第五章 第二次ベルリン危機と同盟の分裂──一九五八~六四年
1 第二次ベルリン危機勃発
分断都市ベルリン
フルシチョフの最後通牒
西側の分裂
ベルリンの壁
2 ドゴールの冷戦
ドゴールの国際政治観
フーシェ・プラン
イギリスのEEC加盟問題
ドゴールのノンとエリゼ条約
3 東欧諸国のソ連への反発
コメコン始動
コメコン改革とルーマニア
キューバ危機と東欧諸国
4 核管理をめぐる陣営内政治
部分的核実験禁止条約
多角的核戦力と核拡散防止条約
ソ連の西ドイツ接近
冷戦の共同支配体制
【コラム5】ドイツの冷戦と第三世界──「民族自決」対「新植民地主義」
第六章 対話と軍拡の時代──一九六四~六八年
1 二国間デタントの進展
西ドイツの二国間デタント
英米の二国間デタント
ドゴールのデタント
2 東側の軍拡と多国間デタント構想
平和覚書
安保会議構想
ウルブリヒト・ドクトリン
東側陣営の軍拡
3 西側の軍拡と多国間デタント構想
NATOの戦略と軍拡
アルメル報告
レイキャヴィク・シグナル
多角的核戦力から核拡散防止条約へ
4 プラハの春
チェコスロヴァキアの改革
ワルシャワ条約機構軍の介入
通常業務
二国間デタントと陣営
【コラム6】地中海・バルカンの冷戦──反ヨーロッパ・デタントの国々
第七章 ヨーロッパ・デタント──一九六九~七五年
1 ブラントの東方政策
ブラントの構想
新東方政策
ポーランドとワルシャワ条約
基本条約と国交正常化
2 欧州安全保障協力会議
西側陣営の変化
ベルリン問題
安保会議と軍縮会議
ヘルシンキ宣言
3 ECとコメコン
ECの成功、コメコンの失敗
ECと冷戦
4 石油危機とヨーロッパ
東西貿易と東欧諸国の経済
石油危機の影響
債務危機
多国間デタント
【コラム7】フィンランドの冷戦──中立国のバランス外交
第八章 混在する緊張と緊張緩和──一九七六~八四年
1 ヨーロッパ・デタントの停滞
ベオグラード再検討会議
軍縮会議
ユーロミサイル危機と二重決定
2 ポーランド危機
「連帯」誕生
ソ連の介入への懸念
戒厳令布告
経済制裁をめぐる米欧対立
3 マドリッド再検討会議
人権と軍縮
休会中の米欧合意
マドリッド会議の妥結
二重決定の実施
4 両ドイツ間のデタント
シュミットとホーネッカー
コールとホーネッカー
陣営の持続
【コラム8】ソ連のアフガニスタン侵攻とEC諸国──幻の中立化構想
第九章 終焉の始まり──一九八五~八九年
1 ゴルバチョフと西欧諸国
ゴルバチョフの新思考外交
ストックホルム軍縮会議
ヨーロッパの核軍縮
ゴルバチョフと西欧諸国の首脳たち
2 ゴルバチョフと東欧諸国
矛盾に満ちた東欧政策
重荷となる東ヨーロッパ
ヨーロッパ共通の家
3 ポーランドとハンガリーの一九八九年
ポーランドにおける「連帯」の復活
ポーランドの準自由選挙
非共産主義者の首相誕生
ハンガリーの急進的改革
鉄のカーテンの綻び
4 NATO諸国の一九八九年
ブッシュ政権と東ヨーロッパ
短距離核戦力と通常戦力の軍縮
一九八九年の陣営
【コラム9】バルト三国の独立と西側の対応──自決の原則はどこへ?
終章 ドイツ再統一とヨーロッパ分断の終焉──一九八九~九〇年
1 ベルリンの壁崩壊
ドイツ問題の復活
東ドイツの破綻
壁の崩壊
ブルガリア、チェコスロヴァキア、ルーマニア
2 ドイツ再統一へ
コールの「一〇項目提案」
ブッシュとサッチャーの反応
ミッテランのヨーロッパ国家連合構想
ゴルバチョフのドイツ再統一受容
東ドイツの選挙
ドイツ再統一とヨーロッパ統合
3 分断の終わり
アメリカの安心供与
ミッテランの拒否
ドイツとヨーロッパの分断の終わり
4 ヨーロッパ冷戦とは何だったのか
安定をめぐる対立
ヨーロッパ冷戦の終焉
一つのヨーロッパへ
あとがき
参考文献一覧
人名索引
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
kk
MUNEKAZ
モリータ
無重力蜜柑
-
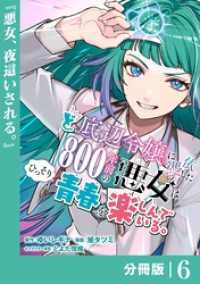
- 電子書籍
- ど底辺令嬢に憑依した800年前の悪女は…
-

- 電子書籍
- 親友の裏アカ【フルカラー】【タテヨミ】…
-
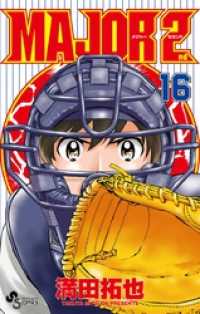
- 電子書籍
- MAJOR 2nd(メジャーセカンド)…
-
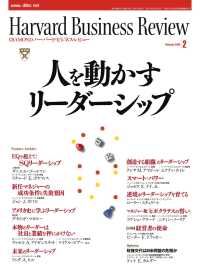
- 電子書籍
- DIAMONDハーバード・ビジネス・レ…
-

- 電子書籍
- 誰にもナイショのラブ&H




