- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
これは恐らく、現存する最後といっていい土葬の村の記録である。
村人は、なぜ今も「土葬」を選ぶのか?
日本の伝統的な葬式である「土葬・野辺送り」が姿を消したのは、昭和の終わり頃とされている。
入れ替わるように火葬が増え、現在、日本の火葬普及率は九九・九%を超える。
土葬は、日本の風土から完全に消滅してしまったのだろうか。
筆者は「土葬・野辺送り」の聞き取り調査を三十年にわたって続け、平成、令和になっても、ある地域に集中して残っていることを突き止めた。
それは大和朝廷のあった奈良盆地の東側、茶畑が美しい山間にある。
剣豪、柳生十兵衛ゆかりの柳生の里を含む、複数の集落にまたがるエリアだ。
日本人の精神生活を豊かにしてきた千年の弔い文化を、まだ奇跡的に残る土葬の村の「古老の証言」を手がかりに、詳らかにする。
【本書の内容】
はじめに
第一章 今も残る土葬の村
第二章 野焼き火葬の村の証言
第三章 風葬 聖なる放置屍体
第四章 土葬、野辺送りの怪談・奇譚
おわりに
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
116
父が亡くなった時は当然のように火葬に附した。遺骨が骨壺に納まってしまうと一応の決着がついた気分になったが、もし土葬であったら様々な儀式や遺体の処理に耐えられたとは思えない。つまり近代日本が土葬から火葬への変更を促したことで「死」を日常から非日常へと押しやった果ての結果なのだ。宗教で土葬が支えられていない日本では、いずれ消滅するだろう。最後に著者は言及していないが、天皇が亡くなると火葬されず陵墓に葬られる。つまり本書で描かれた土葬が絶滅しても皇室のは残るわけだ。いずれ土葬される日本人は天皇家だけになるのか。2021/03/29
六点
111
以前、感想欄に書いているが、六点の父の実家は、中央構造線沿いのど田舎にあった。六点高3の冬に、その実家に住まいしていた祖母が亡くなり、土葬の葬儀を体験することができた。この本の中に出てくる幾つかの集落にも足を踏み入れた事があり、懐旧の情に浸ること無きにしも非ずであった。「過去の消滅した遺制」や「土葬そのものが法的に禁止」と言った誤解があり、消滅の一途を辿っている風習である。恐らく最終的には地所の問題で消滅する他無いと、未だ思う。構成員が共同体に別れを告げ、その傷を如何に癒やしたか、を、追体験して欲しい。2022/04/23
fwhd8325
97
もっと難しい内容かなと思っていましたが、すんなり読むことができました。確かに土葬の時代があって、怪談なんかはその設定が重要だったりしていると思います。土葬の村に葬儀会社が入り火葬中心になったエピソードも面白い。葬祭後の穢れの話は興味深く、人が亡くなることの意味がもっと密接だったように思いました。関係ないけれど、霊柩車を見たときや葬儀が行われている場所を通るときに親指を隠したり、子どもの頃、葬儀の場所を通るとお菓子をくれたりしたのは、何らかの意味があったのだと思いました。2021/05/23
ヒデキ
73
職場の近くの数件の本屋さんに平積みしてあったので 手にとってみました。 職場近くの地域が、幾つか紹介されていたので 土葬の文化が、まだ伝わっているんだなと思いました 家の周りが、浄土真宗なので火葬が当たり前だと思っていましたが、宗派、土地によっておくる形は、色々あるんだなあと思います。2021/09/04
つちのこ
62
土葬はすでに消滅した風習であると思っていたが、まずはその認識を改めなければならない。ほぼ100%の世界一の火葬率を誇る日本にあって、ほんの数年前まで近畿地方の村では行われており、その弔いの実態は地方色ある奇異な風習として受け継がれていた。納棺や野辺送りの作法にも濃密な土俗信仰が背景に見てとれるが、なかでも四十九日に墓をあばく「お棺割り」という風習には戦慄を覚えた。大がかりで面倒さゆえ、多くの人々の協力を必要とする“おごそかな儀式”土葬は住民どおしの連帯感があってこそだが、⇒2021/12/13
-

- 電子書籍
- ママ、やめます~余命一年の決断~ 10…
-
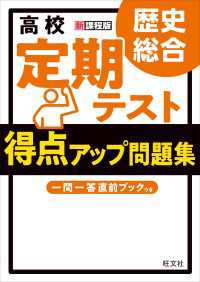
- 電子書籍
- 高校 定期テスト 得点アップ問題集 歴…
-
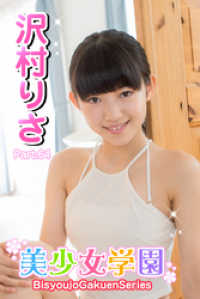
- 電子書籍
- 美少女学園 沢村りさ Part.64 …
-
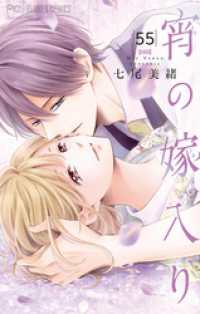
- 電子書籍
- 宵の嫁入り【マイクロ】(55) フラワ…





