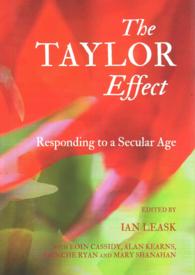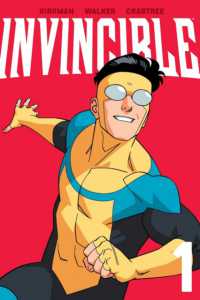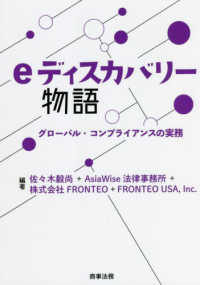内容説明
注意は適応的に行動し、身の回りのものごとを認識するために欠かせない機能だが、その多面性のために定義が難しい。本書は注意を認知システムのバイアスとして捉え、さまざまな研究の結果を裏付けに解説する。注意研究を牽引してきた著者による、これから研究を始める人や、注意の基本的な性質を知りたい人にとって最適の一冊。
目次
はじめに
第1章 注意とは何か
1.1 注意を定義する難しさ
1.2 なぜ注意が必要か
第2章 空間的注意
2.1 わかるプロセスと注意
2.2 空間選択手段としての眼球運動
2.3 空間的注意を測る
2.4 2種類の空間的手がかり
2.5 さまざまな空間的手がかり
2.6 注意のスポットライト
2.7 注意の解像度
2.8 注意をズームレンズに喩える
2.9 さらに柔軟な空間的注意の配置
2.10 注意が向いたところでは何が起こっているか
第3章 特徴に基づく注意
3.1 抜き打ちテスト法
3.2 ブロック法
3.3 状況依存的注意捕捉手続き
3.4 特徴に基づく注意選択と神経活動
3.5 物体に基づく選択
3.6 選択するということは
第4章 視覚探索
4.1 探索のしやすさを左右する要因
4.2 探索関数
4.3 特徴統合理論
4.4 特徴統合理論の修正
4.5 探索をサポートするメカニズム
4.6 注意の停留時間
4.7 探した位置で起こっていること
第5章 注意の制御
5.1 注意制御に関わる神経基盤
5.2 注意捕捉を調べる4つの手法
5.3 ボトムアップ説とトップダウン説の論争のゆくえ
5.4 注意の窓
5.5 注意制御が効くまでの時間
5.6 注意制御と記憶
5.7 作業記憶との相互作用
第6章 注意選択の段階
6.1 初期選択理論
6.2 初期選択理論の修正
6.3 後期選択理論
6.4 初期選択理論と後期選択理論の検証
6.5 注意の漏れとスリップ
6.6 知覚負荷理論
6.7 知覚負荷理論のその先に
6.8 希釈理論
6.9 注意容量配分の自動性
6.10 分割注意と二重課題
6.11 注意の容量理論
6.12 課題切り替え
6.13 注意の容量・資源と再回帰処理
第7章 見落としと無視
7.1 変化の見落とし
7.2 非注意による見落とし
7.3 低出現頻度効果
7.4 その他の見落とし現象
7.5 空間無視
7.6 見落としは防げるか?
7.7 注意の裏側
おわりに
引用文献
索引
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アルカリオン
ニッポニテスは中州へ泳ぐ