- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
新型コロナ克服のヒントは「歴史」にあり。
近代日本は「流行病」「難病」との闘いの連続だった--。
明治天皇や陸海軍兵士たちが悩まされた脚気から、軍民に蔓延したスペイン風邪などの伝染病、「亡国病」と恐れられた結核やマラリア、患者が増える中で治療法の模索が続いてきた精神疾患、現在死因トップのがんまで、日本人は多くの病気に悩まされてきた。
そして今また、「新型コロナウイルス」という未知の病が襲来している。果たして、この新たな感染症といかに向き合うべきなのか。
〈人類の歴史は、一面では感染症(伝染病)との戦いの歴史でもあった。だが戦うと言っても、一方的な防戦と敗北の連続で、十四世紀のペスト流行では欧州大陸の住人の半分近くが倒れ、人々は全滅の恐怖におののいた。
ようやく勝機が訪れたのは、病原である細菌やウイルスの正体が見え始めた、たかだか二百年前からである。(中略)
だが戦いが終ったわけではない。〉
「第八章 新型コロナ禍の春秋」より
本書は、医師や医療専門家ではなく、政治史や軍事史を中心に研究・執筆を重ねてきた現代史家の手になる医学史である。そのため、医学の研究書とは異なり、歴史家の視点から「難病の制圧をめざす国家的な総力戦」の過程を検証しつつ、「人間の生死をめぐって運と不運、喜びと悲しみが交錯するドラマ」を描きだしている。
新たな疫病が猛威を振るう今こそ知るべき“闘病と克服の日本史”。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Daisuke Oyamada
11
近代日本は「流行病」「難病」との闘いの連続だった。 著者は、医師や医療専門家ではなく、 政治史や軍事史を中心に執筆を重ねてきた人です。 そのため医学の研究書とは違い、歴史家の視点から 「難病の制圧をめざす国家的な総力戦」 そんな過程を検証しつつ、 「生死をめぐる運と不運」 「喜びと悲しみの交錯ドラマ」 そんな感じでしょうか。笑 明治天皇や陸海軍兵士たちが・・・ https://190dai.com/2023/06/25/病気の日本近代史-幕末からコロナ禍まで-秦郁彦/2023/06/22
nagoyan
8
優。新型コロナ流行を機に2011年刊行の単行本を大幅に加筆・改訂して新書化したもの。1章では華岡青洲らの医学黎明期、虫垂炎などの外科手術。2章では脚気論争。陸海軍や帝大の権威主義、権力志向と病気。森林太郎(鷗外)らの原理主義的な態度が、大勢の兵士を死なせた。日清戦争、日露戦争の最大の敵は脚気。3章は伝染病。4章は結核。5章ではマラリアが扱われる。脚気に苦しんだ日清、日露両役の反省なしに戦争に突き進み、大量の戦病死者を出す。6章は精神医学の受容と闇。7章は肺がんとタバコ。健康ファシズム批判。8章はコロナ。2021/04/04
かみかみ
3
内容はタイトル通り。興味深かったのは医学と政治・軍事の関係について。明治期の脚気の原因を巡って栄養不足説と病原菌説で意見が割れ、森鷗外(林太郎)が後者の意見に固執して日露戦争で麦飯を白飯に強行的に変更させたために軍内で脚気が蔓延したことは教訓として銘記しておくべきだと思った。肺がんに関する章は著者が愛煙家であることを差し引いても、喫煙率減少と肺がんの死亡者数に相関性が見られなかったことは興味深い。2021/04/15
とり
2
第7章 肺がんとタバコが印象に残った。喫煙率は1960年頃は80%だったが、現在は30%未満まで減りつつけている。一方で、肺がんによる死亡率は1960年から増加傾向にある。肺がんの原因=ほぼタバコだと思いこんでいたが、必ずしも一番の原因でもないらしい。2024/04/17
晴れ
1
どれだけ医学が進んでも次から次へと新しい病気が出てくるのなら、いちばん大事なのは医者の頼るのではなく自分で体力をつけて耐えられるようにしておくことかと思います。2024/05/19
-
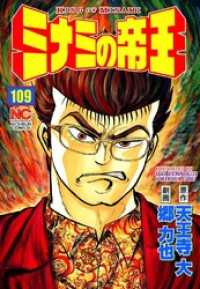
- 電子書籍
- ミナミの帝王 109








