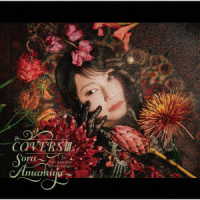- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
太古の昔から人類は生きるためにものを作り、使いつづけてきた。歴史学と経済学の知見を活用しつつ、この経済システムの時間的な流れを明らかにし、歴史のなかで登場した諸システムの特徴のメカニズムと変化のプロセスを追う「経済史学」――その定義、歴史と展望、そして成果をコンパクトに一望する、入門書の新しいスタンダード。
目次
目 次
はじめに
序 章 ウォーミングアップ─経済史学の定義と方法論
経済史学と歴史学
経済史学と経済学
方法論というアポリア(難問)
帰納的方法と演繹的方法、個性記述科学と法則定立科学
経済史学における分析手続
本書におけるアプローチ
読書案内
第1章 狩猟採集経済
人類の曙
生産者行動理論
続・生産者行動理論
コモンズの悲劇
コモンズの悲劇をモデル化する
生産性の停滞
読書案内
第2章 農耕革命
農耕革命と定住
農耕革命をモデル化する
狩猟採集経済のデメリットは解消されたか
モラルエコノミー
その後
読書案内
第3章 ファミリービジネス
ファミリービジネスの成立
消費者行動理論
続・消費者行動理論
主体均衡論
ファミリービジネスにおける意思決定
低賃金の経済か、高賃金の経済か
読書案内
第4章 資本主義
資本主義の成立
労働市場のメカニズム
資本主義の成長
無制限労働供給モデル
続・無制限労働供給モデル
資本主義確立の条件
読書案内
第5章 小作制度と問屋制度
もうひとつの途
生産管理機能のアウトソーシング
小作制度をモデル化する
続・小作制度をモデル化する
問屋制度をモデル化する
二つの途の分岐点
読書案内
第6章 産業革命
マルサスの罠
ソローモデルを構築する
ソローモデルを分析する
ソローモデルの政策的含意
イギリス産業革命
日本の経験
読書案内
第7章 企業
企業の時代
完全競争市場のメカニズム
中小企業の意思決定
第二次産業革命
独占の成立
独占企業の意思決定
二〇世紀、そして現在
読書案内
終 章 クーリングダウン─経済史学の歴史
「学史」を学ぶ意義?
経済史学の誕生
経済史学の発展
日本の経済史学
経済史学の現在
その先へ
読書案内
あとがき
文献リスト
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
まさにい
クレストン
Ex libris 毒餃子
omoide12


![E68:エコカレンダー壁掛A4 〈2026〉 [カレンダー]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/44718/4471856022.jpg)