内容説明
二つの国と二つの言語。夭逝した芥川賞作家の内面の葛藤を描く長篇小説――若くして亡くなった、在日韓国人女性作家。日本で生まれ育ち、韓国人の血にわだかまりつつも、日本人化している自分へのいらだちとコンプレックス。母国に留学し直面した、その国の理想と現実への想い。芥川賞作家の女の「生理」の時間の過程を熱く語る長篇と、「私にとっての母国と日本」という1990年にソウルで、元原稿は直接韓国語で書かれた講演を収録。
◎アイデンティティを追求した李良枝の私小説は、「目に見えない」心のミステリーを解明しようとした鮮烈なテキストなのである。日本から、見知らぬ「母国」へやってきた「刻」の主人公は、だから、母語ではない母国語の文字の前で落ち着きを失う。その「私」の1日においては、だから、一刻一刻、親近感と距離感の間で心のゆらぎを覚えて、最終的には選ぶことができないのだろう。<リービ英雄「解説」より>
-

- 電子書籍
- ハズレ姫は意外と愛されている?【ノベル…
-
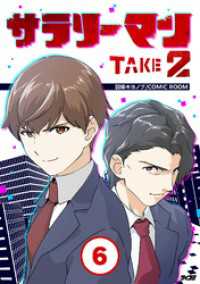
- 電子書籍
- サラリーマン TAKE2【タテ読み】(…
-

- 和書
- 君に光射す
-

- 電子書籍
- 皇帝の伴侶【タテヨミ】第58話 pic…
-

- 電子書籍
- 蚊帳の外 - 本編 ご近所の悪いうわさ…



