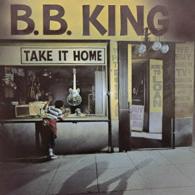内容説明
言葉はなぜ、生まれたのか?人類史上最も偉大な発明である「言語」。その起源をめぐっては、これまで様々な議論が交わされてきた。言語はいつ、誰が最初に使いはじめたのか? 人は言語を突然変異によって獲得したのか、それとも漸進的な変化によって身につけたのか? そもそも、他の動物のコミュニケーションと人間の言語は何が違うのか――すなわち、言語とは何か?ノーム・チョムスキーが提唱した生成文法への反証であるとされた「ピダハン語」の研究で一躍有名となった、異端の言語学者ダニエル・L・エヴェレットが、言語学のみならず、人類学、考古学、脳科学などの知見をもとに、上記の問いすべてに答えを出す。著者渾身の一冊。
目次
はじめに
第1部 最初のヒト族
第1章 ヒト族の登場
第2章 化石ハンターたち
第3章 ヒト族の分離
第4章 みな記号の言語を話す
第2部 人間の言語への生物学的適応
第5章 人類、優れた脳を得る
第6章 脳はいかにして言語を可能にするか
第7章 脳がうまく働かなくなるとき
第8章 舌で話す
第3部 言語形式の進化
第9章 文法はどこから来たか
第10章 手で話す
第11章 まずまず良いだけ
第4部 言語の文化的進化
第12章 共同体とコミュニケーション
おわりに
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
tom
22
いつか、どこかで「言語は遺伝子に組み込まれている」と読んだことがあり、そうなのかと驚いた記憶がある。この本は、遺伝子組み込み説への反論の書。人間の身体構造や脳の中にある短期記憶の在り方、そして狩猟を生業とする集団生活の在り方などなどを積み上げ、言語は遺伝子問題ではない、文化なのだと語る。でもねえ、この本読んでもよく分からない。まあ、人類が始まったときにさかのぼって言語を語るのだから、明確な説明なんてものは無理なことです。著者は、名著「ピダハン」を書いた人。期待したのだけれど、少々残念本で読了。2021/09/29
月をみるもの
21
"「はじめに言葉があった」ヨハネによる福音書" "「いやいや、そんなことはなかった」ダニエル・エベレット"2020/08/20
まふ
10
同著者の「ピダハン」の発展形のようなもの。内容はチョムスキーの言うUL(普遍的言語)が人間の本能に組み込まれた遺伝子の特質であり、突然変異から起こったものであり、誰もが基本的に同じ言語を操る、とする説への真っ向からの反論である。ホモサピエンスはホモエレクトゥスから言語は受け継いでおり、それは記号、類像(イコン)、シンボルを積み重ね音声、音高、イントネーション、ジェスチャー等を総合した形で発生し、文化がそれを支えている、という考え方である。2021/01/22
hal
10
言語人類学者が「言語の起源はホモ・エレクトゥスから始まった」との持論を多方面から展開している。筆者はアマゾン川のピダハンという少数民族の研究で知られる人だそうで、その経験も大きいようです。とても興味深い内容ではあったが、非常に難しく、完全に理解できなかったのが残念です。2020/09/14
izw
8
図書館で借りて半分くらい読んだところで、返却することになり、しばらく間が空いてしまったが、今回後半を読み終えることができた。人類がどのようにして言語を獲得したか、言葉が話された最初はどんな様子であったか、人類が誕生してからの200万年を遡る壮大な謎解きだった。言語はコミュニケーションのために漸進的に形成されたとしたら、コミュニケーションする動物は多いのに、言語を持つのが人類なのは何故か。膨大な研究を紹介しながら、著者の考えを明らかにしていく。2021/08/17
-
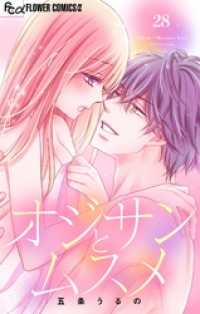
- 電子書籍
- オジサンとムスメ【マイクロ】(28) …