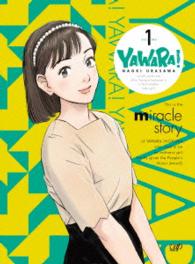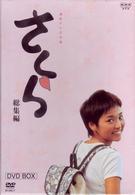- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
極東の島国で資源にも乏しい日本にとって、教育こそが成功と発展の礎だった。ところが今日、事なかれ主義が横行し、いじめや学力崩壊などの現象は改善されず、「教育」は機能不全に陥っている。そもそも日本人を日本人たらしめたものとは何だったのだろうか。近代日本を果敢に生きた九人の生き方と工夫の中から、「教育力」の真髄を汲みとる。
目次
「日本人」力とは何だろうか──文庫化に寄せて
若者はなぜ傷つきやすくなったのか
全体を意識する姿勢が心の安定を生む
「公」と「私」を循環させる
長谷部誠選手の場合
AIと共存する方法
「遠くを見つめるまなざし」について
第Ⅰ部 日本を教育した人々
はじめに
第一章 吉田松陰と沸騰する情熱の伝播
革命家の孵化器「松下村塾」
漢学に培われた松陰の日本語能力
現実にコミットする学問に突き進む
「狂」がつく情熱が人々を感化する
牢獄で看守と囚人を集めて講義を行う
国家の存在に気づいた松陰の視点
興奮を伝達する松陰の教育
松陰のまいた種が明治に花開く
第二章 福沢諭吉の「私立」という生き方
いまだに影響力を持つ実際的な教育者
カラリとした精神と合理的な性格
諭吉に見る学ぶ「構え」
西洋を紹介する濾過器となる
攘夷思想と一線を画す個と国家の独立
独立国家をめざすためにつくられた慶応義塾
学問の目的はモラルを知ること
「権理通義」について
演説の大切さを知らしめた功績
民間の立場でクリアに日本を教育した人
バランス力に優れた諭吉
『女大学』批判にみる諭吉の「ライト」感覚
学ぶことが幸せだった時代に立ち返れ
学びつづける態度を教える教育
第三章 「夏目漱石」という憧れの構造
教師に不向きな教育者
近代日本語の土台をつくる
文化向上に貢献したゲーテと漱石
漢文と落語と英文学の素養が漱石の骨格
日本人に近代的な悩み方を教えたビルドゥングスロマン
漱石の東洋趣味と近代化への葛藤
人間に対する理解の仕方を教える
私たちの内面を耕した漱石の知性と教養
若い人を励まし育てた門人システム
手紙で叱咤激励する教育スタイル
第四章 日本史をつなぐ司馬遼太郎
「日本人とは何か」という問い
日本人としてのアイデンティティを教える
昭和初期は〝非日本人的〟だったという認識
公のために尽くす品格ある日本人を描く
明治は「時代」ではなく、「明治国家」である
武士が武士を倒した不思議な革命
気概がある武士像とモダンなセンスを結びつける
自身が語る「手掘りの歴史」
「明治人」と私たちをつなぐパイプ役
第Ⅱ部 代表的日本人
はじめに
第一章 与謝野晶子の女性力
千年ぶりに表出した女性パワーの炸裂
男性に大きな影響を与えた稀有な存在
人間性を優先し、表現の自由への勇気をもたらす
伝統と近代をつなぐ結節点
近代的自我と論理性
短歌を近代文学の中に位置づける
社会評論家としての活躍
平和や調和を重んじる女性的な原理
男の言葉を使って女性原理を主張する
未熟さゆえの加速度が日本の青春をつくる
第二章 嘉納治五郎の武道力
治五郎が体現する真のエリート像
廃れゆく「武」を近代仕様にメソッド化する
柔術の諸流派を総合し、アレンジした高い知性
格闘技のルールをつくる
「理」を学ぶカリキュラムとして柔道を選択する
型と実践の中から新しい技が開発される
講道館柔道のミッションを受け継ぐ選手たち
「武」の文化を世界に輸出する
「精力善用の精神」の教育
「プロジェクトX」に流れる日本の遺伝子
「作家」夏目漱石を誕生させた教育力
勝海舟や吉田松陰とつながる教育の人脈
上達の普遍的論理を教える
第三章 佐藤紅緑の少年力
少年たちの心に蒔いた種が花開く
放蕩家の本質にある卑怯を憎む純粋さ
文学者ではなく教育者としてのアイデンティティ
連載という形で沁み込んだ心の技
心が柔らかい小学生時代に倫理観を教える
立身出世主義への誤った批判
マンガで教えられる正しい生き方
紅緑、梶原一騎、井上雄彦につらなる系譜
放蕩家の父の血を受け継ぐサトウハチロー
はかない教育事業に大きな役割を果たす
第四章 斎藤秀三郎・秀雄の翻訳力
欧米の文化を日本に根づかせた親子
生涯に書いた著書の量は身長の一・五倍
学習しやすいように工夫された斎藤文法
日本語が持つ言葉の豊かさを証明する
外国語と日本語を地続きにする偉業
全精力を学問と教育に注いだ超人の一生
演奏家としては大成しなかった人
基礎を技化してこそ優れた表現ができる
秀三郎・秀雄に流れる共通の血脈
良き師なくして良き弟子は育たず
第五章 岡田虎二郎の静坐力
輸入思想に行き詰まった人々に浸透した
心身一如の方法として「静坐」を取り上げる
精神の不安な状態を、身体技法をとおして回復する
みぞおちが硬くなった現代人が失ったもの
静坐から生まれた芦田惠之助の国語教育
教育の神髄は自己を書くことにある
身体の構えによって心をコントロールする
姿勢を保てない子供たち
日本の教育力の起源
参考文献一覧
文庫版あとがき
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かずぼん
柏原亜衣
-
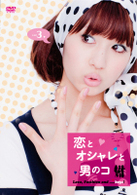
- DVD
- 恋とオシャレと男のコ Vol.3