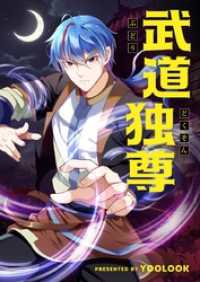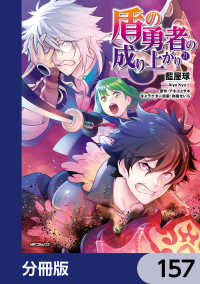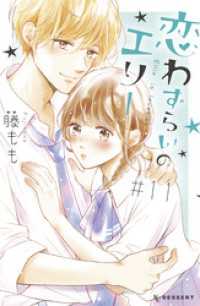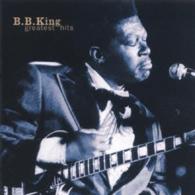内容説明
気鋭の文化人類学者による異色の教育論。高等教育ができることは? 誰もが自分の学びを追求するには? 大学の教育環境が大きく変貌しつつある今だからこそ、知の喜びとは何か根本から考えてみたい。「ほぼ日の学校」の学校長・河野通和氏との対談収録。学生のみならず、新しい視点で世界を見つめてみたいすべての読者へ。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
けんとまん1007
32
まさに、自分自身が学生や大学と関わる中で感じていることが述べられている。年々、ひたすら真面目になってきている学生お、その背景。それは、文科省の意向もある。先生方も、本意ではないが、対応せざるを得ない状況に置かれている。このままでは、ますますイノベーションと遠くなる一方だ。大学は、答えがないことに慣れること、そこから自分なりの価値観でストーリーを作ることを経験する場だと思うのだが。2020/06/10
タカナとダイアローグ
6
図書館本。研究者が教育することの意義について。人文学不要論の系譜で、「英文学部ではシェイクスピアではなく観光向けの英会話を教えるべき」といった旨の提言を受けて、それはマズイ!という軸がある。この発言は冨山和彦氏のものであり、グローバル大学(G型)とローカル大学(L型)の区分けで、L型の大学については実用性といった趣旨らしい。この本ではG型、L型の議論は省略しているけど、どちらにおいても研究マインドの育成は必要だと著者は応えると思う。労働力の再生産は短期的には機能するが、社会が変わった時に対応できないから。2022/11/23
Bevel
5
他の本は好きなんだけどなー。行けるだけで幸福なので大学には「社会的使命」がある。というわりは、「一般社会と同じ論理でそのまま違和感もなく過ごしてしまえるような場に、成長の契機はありません」(社会馬鹿にしてない?)とか、「もし[先生の]その話に違和感を覚えるなら、違う意見を表明してもいい」(権力の非対称性とか考えない?)という感じで、「みなさんがこれから社会で生きていくなかで必要なことの多くは、このゼミの場で学ぶことができます」というけど、そういうふうに授業をデザインできてるようには信じられなかった。2021/05/30
YH
5
本学で教員をされている時は研究者としての側面しか知りませんでしたが、この本を通して、教育に関する考えと想いに共感しました。高等教育関連の書籍で久しぶりのヒットです。 ・問いを立て、それを考えるにふさわしい具体例を見つけ出し、そこから「答え」への道筋を導き出していく。大学では、この一連の作業員を自力で行うことが求められています。でもたぶん、こうした課題がなぜ重要なのか、その意図が学生にうまく伝わっていないp262021/03/26
RENDA
4
友人に薦められて購入。筆者が立教から地方の国立大に転勤した際に感じた、学生の真面目さに対する疑問にはっとさせられた。大学教員になっても、その分野について何でも知ってるわけではないという告白は面白い。大学院に進学予定の自分はなんだかほっとした。2020/05/19