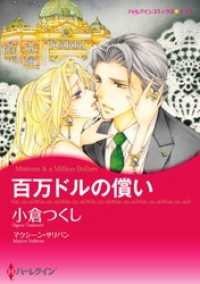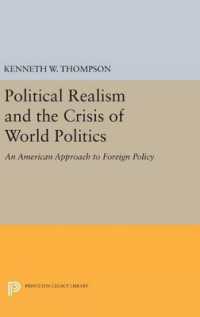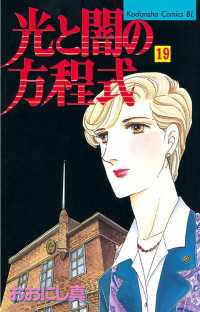内容説明
「東大の先生の本だからどうせ難しいんでしょ」と思ってる人も!
世界史を素通りしてきたり、学び直したいと思ってる人も!
ビジネスパーソンにこそ良質の「リベラル・アーツ」を!
「暗記」じゃなくて「考える」ための、ぜんぜん難しくない「世界史」講義がここに登場!!
人類最大最強のイノベーションは「文字」と「組織」?
「古代」のローマと中国、どっちがすごかった?
アレクサンドロスの遠征はホントに「史上空前の大遠征」だった?
モンゴルとアラブの大征服を比べてわかる、本質的な違いとは?
西欧はなぜ「アジア」を文明的に凌駕したのか?
比べると見えてくる、日本が「西洋化」改革に成功した理由・・・etc.
『紀伊國屋じんぶん大賞2019 読者と選ぶ人文書ベスト30』に選ばれた『文字と組織の世界史』の著者が語り下ろした、ユニークな視点で世界史の動きをつかめる1冊
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ピオリーヌ
10
同著者の近著『文字と組織の世界史 新しい「比較文明史」のスケッチ』をより平易にまとめ直したと言える内容。ラテン文字世界、キリル文字世界、アラビア文字世界、梵語世界、漢字世界と五つの文字世界に着目し世界史を捉え直すという著者の切り口には納得させられる部分が多かった為、当書もすんなり読めた。著者が歴史の研究を本職にしたいと思った理由である、なぜ西欧がアジアを凌ぐようになったのか、そして何故日本がそれに対抗するための西洋化をいち早く成し遂げたのか、を頭にいれると本書がより楽しく読めるのではないか。2022/02/15
武井 康則
5
世界の地域を文化で分ける。その方法として文字を使う。漢字、梵字、アラビア文字、ラテン文字、キリル文字の5つになる。それらが出会うのは大航海時代以後で密接に衝突するのは近代になってから。世界史を年号と事件の暗記から解き放とうと以上の区分けをしてその解説で100ページを費やし、大航海時代では本書の半分に達している。その後も時代を遡り行きつ戻りつ。文章も会話体でどこが重要か埋もれてしまう。詳しくは山川の世界史を読めというのだろう。2025/11/06
Rin
5
世界史の内容を様々な角度から見たいとおもい読んだ。 文字から見る世界史は世界史の教科書にはないし、こう言った本の一冊目としてはよかった。また文字に着目してることもあってか、珍しく10世紀くらいまでを半分以上使って解説していた(歴史はその性質上現代に近づくほど内容は濃くなりがちなのだが)。しかし少し世界史を触れてない人には重いかもしれない。 星22021/10/27
ta_chanko
5
「文字」から世界を読み説く。世界はラテン文字・キリル文字・アラビア文字・梵字・漢字の5系統の文字圏から成り、それぞれ独特な文明を形成してきた。大航海時代以降、西欧(ラテン文字世界)が他地域に対して比較優位を得て、いわゆる「西洋近代」を実現してきたが、21世紀は「文明の衝突」の時代になるかもしれない。著者は23世紀には巨龍(中国)と巨像(インド)が興隆することを予測しているが、短期的には大変な時代になるだろう。2019/10/31
左手爆弾
4
今ひとつ全体のコンセプトがわからないまま読了。大人のための世界史の学び直しなのだとすれば、ちょっと分量や扱う視点が不足している。もちろん、文明と文化を分け、文字に注目して各地域や文化圏を理解するという試みは「世界史」の本としては悪くないと思うが、そもそも「世界史」とは何なのかということも含めて考える必要があるように思う。あと、昨今のグローバルヒストリーとかの流行をどう考えればよいのかということも、読者として想定される「大人」は考えているのではないか。2020/09/29