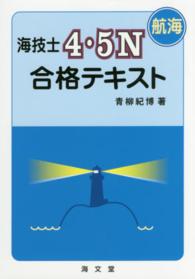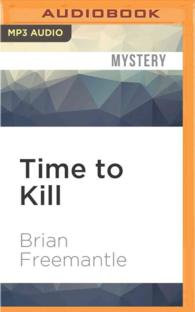内容説明
20世紀フランスを代表する思想家モーリス・メルロ=ポンティ(1908-61)が死の前年にまとめた論集『シーニュ』。同書には、言語学、絵画論、人類学への言及や、フッサール論、ベルクソン論、マキアヴェッリ論など、おもに中期から晩年にかけて執筆された多彩な論考が収録されており、その多中心的な思想を一望するうえで欠かせない一冊となっている。本書ではそのなかから、ニザンとサルトルとの関わりが美しく綴られた序文のほか、「間接的言語と沈黙の声」「哲学者とその影」など重要論考6本をセレクトし、新訳。清新な訳文と懇切丁寧な注釈・解説により、その真価が明らかとなる。
目次
序
間接的言語と沈黙の声
モースからレヴィ ストロースへ
哲学者とその影
生成しつつあるベルクソン
マキアヴェッリについての覚書
訳者解題
索引
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
いとう・しんご
9
読友さんきっかけ。新訳なので読みやすいかなぁ、と思ったけど、なかなかどうして。「哲学者とその影」というフッサールに関する論文が柱だと思ったけれど、「間身体性」「間主観性」「偏差」などのキーワードを通して、絶対に理解できる筈のない他者の痛みを、それでも共有し共感ずることの不思議とそこに垣間見える、ある根源に向き合う哲学者の探求の営みを覗き見ることが出来たような・・・気がしました。2023/02/14
Bevel
6
既訳は逐語訳をしてくれないことがあって、新訳はとても助かる。「間接的言語と沈黙の声」「モースからレヴィストロースへ」あたりが好きな論考。身体から見た強度の世界とその不在がある。その不在を埋める行為(スタイル)に対して一枚の布が与えられて、布の方向づけられた部分を収斂させると出来事が起こり自分も環境も変身する話と、意味のうちに偏差の交換体系としての構造があり、マナと関わりつつも、これが歴史の一形式だという話。全体として、言語、絵画、社会が同じ意味としてあるけど、その関係はどうなっているのだろうと思っている。2023/01/04
nranjen
6
メルロ=ポンティのシンポジウムを拝聴して興味を持ち、とりあえず大学生協で売っていた文庫本を購入してみた。頑張って一気読みしようとしたら、フッサールとベルグソンで息絶えていて、マキャベリは記憶ない。自分の興味関心は絵画論と身体論が結びついているところにあることを発見(序とソシュールのところ)。単行本を読むならそちらの路線で行きたい。サルトルとニザンについての言及は若き日の、というよりも何かしら痛々しさを感じずに読めない。1950年代の思想は初めてなので新鮮。2021/05/06
momonori
3
フランスの哲学者。生前はサルトルとも交流があり、フランス現象学の発展に多大な寄与をしたとされる。本書は亡くなる直前にまとめた論考集からの抜粋版。初めてメルロ=ポンティの著作を読んだが、さすがに難解であり、一読してすぐにわかるような内容ではなかった。個人的にはヘーゲル以降の哲学者においては、ヘーゲルをどのように評価するかというところが重要だと思っている。メルロ=ポンティはヘーゲルの「真理」はあくまで〈対自〉的なものであり、そこに客観性をもたないがゆえに、プラトンやデカルトの真理からは距離を取っていると見る。2025/07/01
Ex libris 毒餃子
3
登録もれ。
-
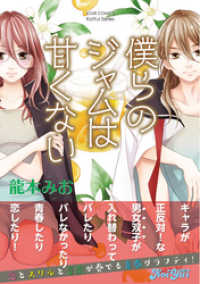
- 電子書籍
- 僕らのジャムは甘くない 分冊版 27 …
-

- 和書
- 骨は珊瑚、眼は真珠