内容説明
息苦しいこの世界からの出口は、ある。
片づけコンサルタント「こんまり」のメソッドは、
自分とモノとの純粋な対話ではなく、自分自身との対話を目指すものなのではないか。
アニミズムとは、地球や宇宙における存在者のうち、人間だけが必ずしも主人なのではないという考え方だとすれば、自分との対話を目指すのは、人間のことだけしか考えていないという意味で、真のアニミズムとは呼べないのではないか。
本書の出発点は、ここにある。
アニミズムは「原初の人間の心性」として過去のものとされてきた。
しかし、そこには、人間の精神を豊かにするヒントが隠されているのではないか。
文学、哲学の大胆な解釈とフィールド経験を縦横に織り合わせて、「人間的なるもの」の外へと通じるアニミズムの沃野を探検する。
人間が世界の「主人」をやめた時、動物、モノ、死者との対話がはじまる。
【目次】
1 こんまりは、片づけの谷のナウシカなのか?
2 風の谷のアニミズム
3 川上弘美と〈メビウスの帯〉
4 壁と連絡通路――アニミズムをめぐる二つの態度
5 往って還ってこい、生きものたちよ
6 東洋的な見方からアニミズムを考える
7 宮沢賢治を真剣に受け取る
8 まどろむカミの夢――ユングからアニミズムへ
9 純粋記憶と死者の魂――ベルクソンとアニミズム
10 記号論アニミズム――エドゥアルド・コーンの思考の森へ
11 人間であるのことの最果て――語りえぬものの純粋経験
12 人間にだけ閉じた世界にアニミズムはない
あとがき
参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
tamami
43
久しぶりの県内大型書店。大量な本の森にクラクラして、思わず山東さんのアニミズム、人類学者、奥野克巳のキーワードに反応して手に取る。こんまり、ナウシカから川上弘美、西田幾多郎等々の著作・言動にアニミズムとは何かを探っていく。実に面白い。探求の泥沼に嵌まりそうである。著者は、「アニミズムは、自らに閉じてしまうのではなくモノや他者との関係に開かれて、こちら側とあちら側を往還し続けることによって、その必然として見えてくる世界のこと」と記す。謂わば定義であるが、面白さの中身はそれぞれの精神による実践に懸かっている。2022/03/25
アナクマ
38
文化人類学の枠を取っぱらいアニミズムを広く考える。前半の7章まで。◉こんまり(編者の力量よ!)、ナウシカ、川上弘美。アイヌの送り儀式。メビウスの帯。池澤夏樹「クマになった少年」。生きもの供養碑。そして宮沢賢治。◉境界線が失せること。あちらに往くだけでなく、こちらに還ってくること。アニミズムが先か仏教が先かの見解は一致していないそう。◉モノにも魂がある、という話ではなくて、人がモノに投影する心象、モノとのやりとり自体の重要性を指しているのだと理解しておこう。わからない言葉や概念が多いけど、考えるパーツに。→2021/02/19
テツ
15
ほんの少し前までは地球に霊性が溢れていた。森羅万象に人格(神格)を見出し、彼らの為すことに喜び悲しみ畏れ敬ってきた。霊長などと名乗り驕りだしてから少しずつそうした存在が目に入らなくなってきたけれど、現代社会においても、ふとしたときに空を見上げたり、樹木に触れたり、水に浸ったりしたときに、何かわからない大きな存在と触れ合えたように思える瞬間がある。それがあれば寂しさが消えるような触れ合い。この地球に人間しか存在していないとする世界観は、とても冷たく寂しい2022/03/25
おーすが
11
「いのちが石の中にあるというのではなくなる。むしろ、石がいのちの中にある」(オブジワの長老の言葉)こんまりの片付けメソッドに見る現代社会のアニミズムから人類学史に見られるアニミズムの分類まで、充実した内容。アニミズムとは自然に魂を見出すという自発的な行動だけではなく、無意識下の意識にあらわれるかたち。ウィラースレフのユカギール狩猟民の話『ソウル・ハンターズ』が素晴らしい。絶対他者との同化こそ癒しであると感じる。宮沢賢治、クラークの考証も良い。そのうち再読したい。2024/02/07
Kyohei Matsumoto
8
自分も普段似たようなことを考えているような気がする。いろんな有名な学者の論をいろんなところで使用しているが、結局どれも自分が学んだことのある学者ばかりだった。大事なことはアニミズムというこの思想をいかにして現実の社会や現実の生活に落とし込むかということだと思う。あるいはそのような体験を芸術としてうまく表現するかとか。まだ古来の生活が残っているところはたくさんあるが、ほとんど消失しているようなところもたくさんある。ここ数十年どう動くかがアニミズムを生活に入れられる人が残ろうかどうかの境界かもしれないと思う。2020/11/03
-

- 電子書籍
- 春驟雨の誘い【分冊版】 2 MFC ジ…
-

- 電子書籍
- 零號琴 下 ハヤカワ文庫JA
-

- 電子書籍
- 24区の花子さん 2 チャンピオンRE…
-
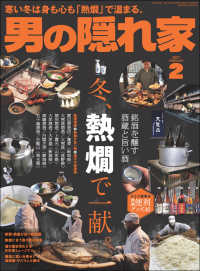
- 電子書籍
- 男の隠れ家 2021年2月号
-
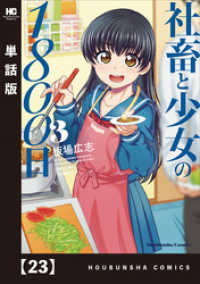
- 電子書籍
- 社畜と少女の1800日【単話版】 23…




