内容説明
どんな言語や方言にも,それぞれに美しい規則の体系がそなわっている.私たちは幼いとき,造作もなくその体系を身につけ,大人になった今は,無意識にそれを操ってことばを話しているのだ.標準語や鹿児島弁のアクセントを例に,一見混沌とした言語現象に潜む法則を見つけだし,自分の頭の中で起こっていることを探ってみよう.
目次
プロローグ┴1 標準語のアクセント┴名前のアクセント┴モーラと音節┴複合名詞のアクセント┴2 標準語と英語のアクセント┴日本語とラテン語のアクセント┴標準語のアクセント変化┴-3の秘密┴3 平板式アクセントの秘密┴ケイコとマナブ┴普通名詞の平板式アクセント┴カラヤンとカンヤラ┴大阪弁のアクセント┴4 鹿児島弁のアクセント┴春子と夏子┴青信号と赤信号┴夏と冬はA,春と秋はB┴AチームとMチーム┴「行く」と「来る」┴5 鹿児島弁のアクセント変化┴紅葉と楓┴調査方法┴調査結果┴鹿児島弁はどこへ行く?┴エピローグ┴参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
hnzwd
21
"パラマサ、ソゴホジョモド"という造語について発音すると、大体の人が同じ発音になってしまう、というアクセントについての裏(?)ルールを解説する本。"おとこ"と"ねずみ"のように単語本体のアクセントは同じなのに、後ろに付ける"が"のアクセントが変わると別グループにするとか、、興味深い。岩波科学ライブラリー楽しいな。2023/11/07
calaf
11
なるほどと納得する部分、ちょっと違う気がすると思う部分、いろいろありました。後者はおそらく、私が関西語圏の人間という事が影響しているのかもしれません。それにしても、鹿児島弁って...そうか、分かりやすいのか。少なくともアクセントに関しては。2013/04/11
ががが
4
再読。ページ数の割りに内容は濃い。アクセントがどのようにしてシステマティックに働いているのかを知ることができる。音の表面にとらわれず、根底で規則を支配している原理の分析の仕方はとても鮮やかで見事というほかない。高校のときに「こころ」という言葉のアクセントをよく間違って発音してると指摘されたが、それはこの単語が日本語のアクセントの中では不規則な振る舞いをするグループに属することがわかってすっきりした。鹿児島弁のアクセント体系とそのシステムの変容もまた興味深い。日本語の音声が違ったものに聞こえてくる。2015/04/04
ががが
4
普段意識していないアクセントに体系がきっちりあることを教えてくれる。大学の授業で日本語学を取ったときはそもそもアクセントの型が識別できなかったけども、本当に母語話者は考えずにアクセントを置いているのだなぁと読んでて思った。しかも日本語特有の法則ではなくてラテン語や英語にも敷衍できる原理が働いていることに少し感動。鹿児島方言の章も興味深かった。内容の割には、量があっさりしているように読んだ後思えた。もっとアクセントについて知りたくなる一冊。2014/09/22
sipsee14
1
平易な例でアクセントに関するデータ(語例)の扱い方やアクセント規則の導き方を体験できる。教科書というよりは導入の読み物で、混み入った議論は触れられておらずアクセント規則の明瞭簡潔さを主とする内容。三省堂の『日本語アクセント入門』と合わせると良さそう。2022/01/22
-

- 電子書籍
- Retry~再び最強の神仙へ~【タテヨ…
-
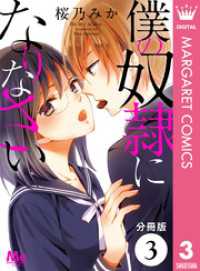
- 電子書籍
- 【分冊版】僕の奴隷になりなさい 3 マ…
-

- 電子書籍
- 今日から使える!宿題のもやもやスッキリ術
-
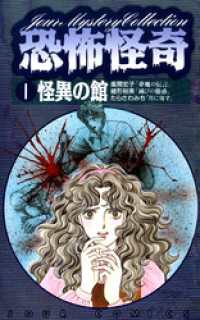
- 電子書籍
- 恐怖怪奇 1 怪異の館 ジュールコミッ…
-

- 電子書籍
- サンキュータツオの芸人の因数分解 - …




