内容説明
名誉と屈辱、本能と理性、男らしさと女らしさ。
太古から現代にいたるまで、人間は、このきわめて「人間的」な暴力とともにあった。
いや、その歴史は、人間の歴史そのものなのだ。
リングにあがった人類学者が描き出す暴力が孕むすべてのもの。
序
1章 人間的な暴力
2章 理性の暴力
3章 殴り合うカラダ
4章 拳のシンボリズム
5章 殴り合いのゲーム化
6章 「殴り合い」は海を越えて
7章 一発逆転の拳
8章 名誉と不名誉
9章 殴り合いの快楽
10章 女性化する拳
あとがき
註
参考文献
目次
序
1章 人間的な暴力
1-1 そこにある暴力
血みどろの共同体/身内の殺害
1-2 闘争の擬態
儀式から見世物へ/闘争を見る喜び/モハメド・アリ―闘争のしゃべり/にらめっこ/目の暴力
1-3 残忍な喜び
矢を射刺された聖人/賛美される残忍さ
2章 理性の暴力
2-1 本能と暴力
世界最強の男/攻撃は本能か/子殺しとリンチ/闘争のプロセス
2-2 口から手へ
人間の本質/「殴る」類人猿/口の武装解除
2-3 遊びと闘争
気晴らしの発生/遊びと成熟/ホモ・ルーデンス/模倣と競争/ラッキーパンチ―運と眩暈/狩猟からスポーツへ/sportの語源/殴り合いのルール
3章 殴り合うカラダ
3-1 殴り合うカラダのイメージ
自転車ドロボーへの復讐/ベイヨーンの流血男/敗者が勝つ物語/ロッキーのカラダ/アスリートのカラダ/かっこいいカラダ
3-2 つくられるカラダ
殴り合いのプロのカラダ/古代ギリシアのスポーツクラブ/拳闘のシンボルは?/太った腹の使い方/減量の職人
3-3 名がつくるカラダ
マサト?コボリ?/「五つ星焼き鳥」のパンチ/リングネームとニックネーム/「海老原」はヤバい!?/姓は「ガッツ」?
4章 拳のシンボリズム
4-1 拳と手のひら
拳の親指/誓いの手のひら/殴る拳
4-2 拳はペニス
ガッツポーズの日/ガッツポーズは文化的/生殖器崇拝/凶暴な拳/殴り合いの挨拶/オバマが広めたフィスト・バンプ
4-3 正義の拳
鉄腕アトム/鉄腕とパンチ/正義の味方はパンチしない/柔よく剛を制する/スーパーマンの誕生/アメリカのニューシンボル/都市労働者のヒーロー/大統領はボクサー/白人男性の「男らしさ」/ヒーローのカラダ
4-4 国家による拳の暴力
拷問と清め/司法との対決/拷問の拳/文化と残忍さ
5章 殴り合いのゲーム化
5-1 闘争のゲーム
戦闘と決闘/決闘というゲーム/殴り合う民族競技/こぶしうち/足技があっても「拳法」
5-2 古代オリンピックの拳闘
ホメロスが語る拳闘/オリンピアの祭典/ソクラテスも拳闘ファン/拳の装着具/古代オリンピックの終焉
5-3 イギリスの拳闘─流血と底力
イギリス初の拳闘試合/初のチャンピオン/ブロートン・ルール/流血の楽しみ/暴力からゲームへ/プライズ・ファイトの急衰
5-4 ボクシングの成立
ボックス!/スパーリングの発生/高貴な自己防衛の技術/プライズ・ファイトからボクシングへ/クイーンズベリー・ルール/時計の時間/流血と底力の排除/決闘の面影
6章 「殴り合い」は海を越えて
6-1 ボクシングは港から
黒船とともに/アメリカのピュジリズム/イギリスとアメリカのチャンピオン対決/金メッキ時代の殴り合い/日本初のボクシング/横浜のメリケン練習所/異種格闘技の人気
6-2 「一石四鳥」のスポーツ
柔道対ボクシングのケンカ/日本ボクシングの発足/キャッチコピーは「東郷」/メリケンから拳闘へ
6-3 「拳闘」がやってきた!
ボクシング史の時代区分/初のスーパーアイドル・ボクサー/血の十回戦!/ヤクザも覆せない判定/槍とピストン
6-4 玉砕から科学へ
ほか
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
tom
kenitirokikuti
imagine
の
minami
-
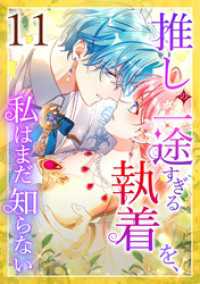
- 電子書籍
- 推しの一途すぎる執着を、私はまだ知らな…
-
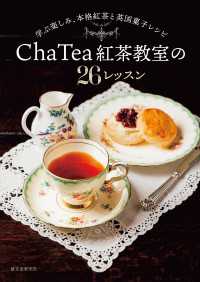
- 電子書籍
- Cha Tea 紅茶教室の26レッスン…
-

- 電子書籍
- その魔女を放せ第34話【タテヨミ】 モ…
-
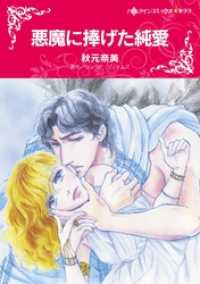
- 電子書籍
- 悪魔に捧げた純愛【分冊】 11巻 ハー…
-
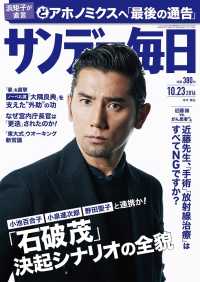
- 電子書籍
- サンデー毎日2016年10/23号




