内容説明
陸軍と海軍とのいがみあいは、どの国でも語られている。平時は予算の争奪戦、戦時は手柄の取りあい、責任のなすりあいとなる。縄張り意識が強い日本人の民族性だけでは説明がつかない、対立の成り立ちを解明する。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
CTC
12
19年4月の光人社NF文庫新刊。単行本は09年同社で、初出は『丸』の連載。建軍から自衛隊に至るまで、タイトルそのものをテーマに圧倒的知識量と論理的考察で語っていく本書は、発見の連続で驚くばかりだった。本書を読めば海軍善玉論は笑止千万だとすぐさま諒解できるのは当然として、共同謀議どころか陸海軍の間で共通の戦争目的すら覚束ないのだから。。総力戦研究所が出来て陸海軍民合同で戦争体制を研究し始めたのは16年4月だったそうだが、機材の共用や弾薬(口径)の統一すらしないとは、行き当たりばったりそのものだろう。2019/07/04
たかしゃん
1
一部の作家の影響か、海軍善玉論が信じられてきたが、実態は、岡敬純や石川信吾のような対米強硬派が中央にいた。 敵を見ずに陸軍ばかりをみて、陸軍と同等の権利獲得奔走する海軍は、現代の省益を求めるお役所と同じだったと思う。永年、アメリカを仮想敵国とし、予算を確保してきた海軍としては口が裂けてもアメリカと戦えませんとは言えなかった。 ところで、高校生の時、江藤淳の海は甦るを読んで、若かりし山本権兵衛に胸を熱くしたが、山本権兵衛が海軍の過剰な権利獲得運動の元凶のような気がする。2020/01/18
江川翔太郎
0
日本の国軍ができた当初は陸海軍のトップ同士が顔見知りで、うまく連携できていたことが分かりました。特に日清戦争の栄城湾の上陸では第二次世界大戦での上陸作戦とほとんど変わらない完成度の指揮系統が出来ていた事に驚きました。 しかし、世代交代が起こり、陸海軍同士の交流がなくなってしまったせいで連携が出来なくなり、何でもかんでも平等といった風潮が生まれ、少ない国力を活かすことができなくなっていたので、軍の上層部同士はきちんと交流しないといけないと思いました。2019/08/30
-

- 電子書籍
- 美少女学園 玉城ひなこ Part.55…
-
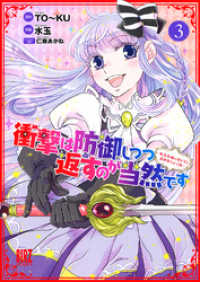
- 電子書籍
- 衝撃は防御しつつ返すのが当然です (3…







