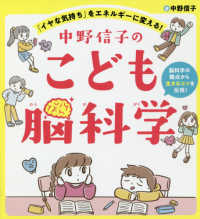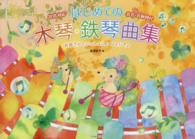内容説明
ネパール東部、ソルクンブ郡。エベレストの南麓にあたる北部のクンブ地方は、“勇敢で忠実な山岳民族”と謳われるシェルパの人々の居住地である。標高三〇〇〇メートルを超えるこの険しい山岳地帯では、山道は天候によって質感を変え、しばしば土砂崩れや降雪によって流失しては再び姿を変えて現れる。
ヤクを追うシェルパたちが自給自足に近い暮らしを営んでいたこの地域は、次第に山岳観光の名所として知られるようになり、現在では年間数万人もの観光客が訪れるようになった。シェルパの人々はヒマラヤ登山の手助けをして働くようになり、ネパール各地からはポーターやガイドなどの職を求めて、「シェルパ」を名乗る多様な出自の人々も集まってくる。
変転する自然環境のなか、観光客のために道を見出しながら山中をゆく彼らとの出会いは、存在をめぐる根源的な問いへと通じていた――「世界」「自己」の自明性をゆるがすフィールド体験をもとに、ティム・インゴルドらの議論を補助線にして気鋭の人類学者が描き出す、刺激的なエスノグラフィ。
世界を歩むとき、自己は道であり、道は自己である
われわれは世界のうちで無数の人やモノや事物と対等な関係のなかで生を営んでおり、人間社会とはそのうちの一部を恣意的に切り出したものに過ぎない。そしてわれわれが一歩を踏み出すとき、自己の身体は他者の身体やモノや概念からなる環境中の諸要素とそのつど一回的な関係を取り結び、道のアレンジメントの一部となる。世界を歩むとき、自己は道であり、道は自己である。(本文より)
電子版では写真をすべてカラーで掲載しています。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
榊原 香織
まさ
sayan
鯖
kuukazoo