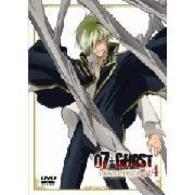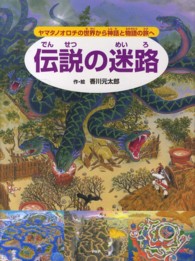内容説明
若き中国人研究者が読みとく日本文化の死角。
新進気鋭の中国人研究者による、斬新な日本文化論。四川省出身の著者・彭丹氏は、四川大学で日本文学を学び、中国西南航空公司勤務を経て日本留学。中国の航空会社に勤務した後、日本に留学。現在は法政大学講師。来日以来、疑問に思ってきたことは、中国では廃れた文化が日本に残っていることだった。それを最も意識したのが、茶の湯の茶道具であった。茶の湯で珍重される茶碗のほとんどが唐物(中国製)で、しかも国宝茶碗もほとんどが唐物である。日本の国宝であるはずなのに。しかも不思議なことには、産地・中国にはそれらの茶碗は何ひとつ残っていないのだ。なぜ日本の茶人は唐物を珍重したのか。なぜそれらが中国に残っていないのか。そこに見え隠れする、「借用」と「創造」という、日本文化の本質。それを解きあかしていくのが、本書である。日本人だからこそ気づかない、日本文化に潜む中国文化の影。中国人の視点から、茶の湯、そして国宝という、日本文化の美意識の聖域に踏み込んだ、まったく新しい比較文化論の誕生である。
※この作品は一部カラーが含まれます。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ホークス
32
中国人の文化比較研究者が、茶道体験と日中の陶磁研究を元に日本文化を読み解く。天目茶碗の考察が特に興味深い。感覚的だが、中国は美術に対してユニバーサルと言うか、技術の高い物や豪華な物を額面通りに重視する感じがする。曜変天目の美しさは「侘び茶碗」と違い万人に判るものだが、生産地の中国で好まれず日本にしか残っていない。その謎を日中それぞれの文化の変遷から解明するくだりは説得力があった。他、祥瑞や龍文の話も含めて検証が詳しく自分は消化不良だが、本書を通じて中国的感性の一端に触れられたのは良かったと思う。2018/02/13
R
25
なぜ、中国で作られた茶碗の多くが日本にあり、また、日本で評価されているのか。これをとても不思議だと感じた中国の方から見た、文化史をつづった本でした。興味深い考察もあり、読みどころが多いのだけども、自分が日本人だからか、どこか納得できないところもあり、議論をしたくなる内容。まず中国ありきで、そのカウンターとして日本の文化が醸成されたという風にもとれる内容なので、なんとかこれに反論する言葉を得たいと思った。耀変の不思議や、歴史の謎に挑む部分もあり面白かった。2018/02/19
宇宙猫
24
挫折。抹茶茶碗に興味があったんだけど、専門的すぎた。2015/12/19
デューク
5
中国生まれで、日本文化研究者である筆者による、日本と中国の比較文化論の決定版。 筆者は日本の茶道を学ぶうち、奇妙なことに気付く。千利休らが愛した茶器は多くが中国産であるが、本場の中国では雑器として扱われているものばかり。古いものや外から来たものを自家薬籠中の物にする日本文化と、革命方式で古いものを一掃する中国文化。2自国文化を知ることは、他者との比較をすること、それができる外国人の視点を借りることの重要性を、再確認させてくれる一冊。いちおし2017/09/11
tkokon
4
【興味深い】陶磁器について全く予備知識なく読み始めたが、興味深く読み進められた。日本の国宝となっている陶磁器14点のうち中国製が9点。茶碗では国宝8点中5点が中国製。しかし、同時代の中国ではほとんど評価されないものも多いという。砧青磁、珠光青磁、曜変天目、油滴天目、禾目天目など、初めて知る言葉ばかりだが、いつの時代に中国で作られ、いかにして日本い渡り、なぜ重宝されるようになったのか、筆者の仮説が楽しく読める。良いモノのなかで、時代に合致し、特別な意味合いが付与されるものが国宝として後世に記憶されるのだ。2016/01/06
-

- 電子書籍
- 輪廻の巫女~時を超え、大神様から寵愛さ…
-
![民法演習 はじめて解いてみる16問[固定版面]](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-1961533.jpg)
- 電子書籍
- 民法演習 はじめて解いてみる16問[固…