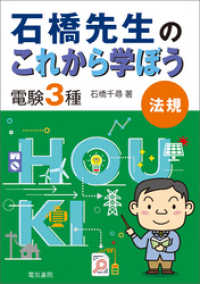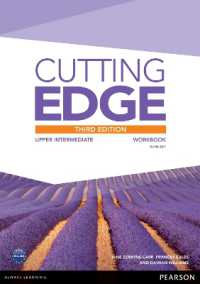内容説明
平成27年改正特許法(平成28年4月1日施行)における実務の指針となるべく、職務発明制度を丁寧に概観したうえで、いかなる運用が許容されているのか及びあるべき運用とは何かを詳説し、関連する裁判例を紹介、より具体的な悩みどころについてQ&Aで道筋を示す。さらに、職務発明規程等の書式も提供する、「実務で使える」解説書!
目次
第1章 職務発明制度の内容及びその変遷
1 職務発明制度とは
(1) 職務発明制度の概要
(2) 「職務発明」該当性
2 平成16年改正前の職務発明制度
(1) 法定通常実施権(平成16年改正前特許法35条1項)
(2) 予約承継(平成16年改正前特許法35条2項)
(3) 相当対価請求権(平成16年改正前特許法35条3項)
(4) 職務発明規程等による対価決定(平成16年改正前特許法35条4項)
コラム:職務発明制度の基本構造整備の始まり(大正10年特許法)
3 平成27年改正前の職務発明制度
(1) 法定通常実施権(平成27年改正前特許法35条1項)
(2) 予約承継(平成27年改正前特許法35条2項)
(3) 相当対価請求権(平成27年改正前特許法35条3項)
(4) 職務発明規程等による対価決定(平成27年改正前特許法35条4項)
(5) 職務発明規程等によらない対価決定(平成27年改正前特許法35条5項)
4 現行特許法(平成27年改正後)の職務発明制度
(1) 現行特許法における職務発明制度
(A) 現行特許法35条1項
(B) 現行特許法35条2項
(C) 現行特許法35条3項
(a) 概要
(b) 文言の解釈
(c) 効果
(ア) 特許を受ける権利が共有に係る場合の帰属の不安定性の問題への対応
(イ) 二重譲渡問題への対応
(d) 本条の定めと第1項の定めの関係
(ア) 原始従業者帰属の場合
(イ) 原始使用者帰属の場合
(D) 現行特許法35条4項
(E) 現行特許法35条5項
(F) 現行特許法35条6項
(G) 現行特許法35条7項
(2) 施行期日及び各規定の適用基準
(A) 施行期日
(B) 現行特許法の職務発明に係る各規定の適用基準
(a) 使用者帰属に係る規定(現行特許法35条3項)の適用基準
(b) 相当の利益に係る規定(現行特許法35条4項・5項・7項)の適用基準
(c) 職務考案及び職務創作意匠
5 職務発明ガイドライン
6 報告書から見る平成27年改正後の実務動向等
(1) 平成27年改正に伴う職務発明規程の改訂状況
(2) 原始使用者帰属の採用
(3) インセンティブ制度の改定
(4) 職務発明に関するルールの実態
(5) 手続3要素の履践状況
第2章 実務Q&A
【Q1】
「使用者等」、「従業者等」の意義は何か。出向社員や派遣社員が職務発明をした場合、当該職務発明について特許を受ける権利は誰に帰属するのか。
【Q2】
現行特許法35条3項の職務発明について「特許を受ける権利が発生した時」とは「発明の完成した時」を意味するところ、「発明の完成」 とは何か。
【Q3】
現行特許法35条3項が適用されて原始使用者帰属となる場合の発明者は誰か。
【Q4】
使用者は、原始使用者帰属と原始従業者帰属をどのように使い分ければよいのか。現行特許法35条2項と3項との棲み分けはどうすべきか。
【Q5】
原始使用者帰属とするための要件は何か。
【Q6】
いかなる職務発明規程であれば、現行特許法35条3項が適用されて、原始使用者帰属となるか。
【Q7】
いかなる職務発明規程であれば、特許法において、原始従業者帰属となるのか。
【Q8】
ほか