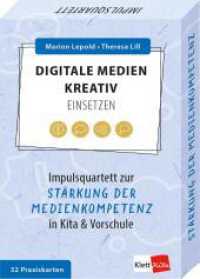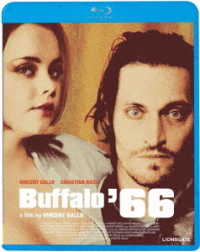内容説明
『哲学探究』は、ウィトゲンシュタインの後期の主著として、哲学史上に燦然と輝く名著です。
すでに、邦訳も出ていますが、古すぎたり、哲学としての解釈に不足があったりして、歴史的な名著の割には、名訳に恵まれませんでした。
このほど、もっとも信頼のおけるテキストである最新第4版の版権を取ることができました。
翻訳は、現在の日本で、もっとも厳密かつ魅力的な研究を続けている鬼界彰夫氏が担当します。
鬼界氏は、『哲学探究』というテキストが、どのような構造になり、何をめざしているのか、日本語で明確にわかるよう、特に版権所有者の許可を得て、見出しや解説等を、十分に入れていきます。
この企画によって、ついに、決定版の『哲学探究』の訳が世に出ることになったのです。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ころこ
31
訳が優れているかどうかは分かりません。訳者を信じるしかないでしょう。アフォリズム形式ですがそれぞれが有機的につながっており、重要な議論の塊と重要ではない塊を区別して、濃淡をつけることが読書のコツだと思います。訳者によると、支配的主題に関する思考運動(ムーヴメント)から派生する下位主題(スレッド)を同定し、そこで扱う独立した思考のまとまり(シークエンス)に区切って分析する。それが「規則に従う」だったり「私的言語」ということのようです。「規則に従う」とは、「規則に従うという規則に従う」とは「規則に従うという規2020/11/27
田氏
24
前作『ろんてつ!』の大ヒットから、続編が待たれること32年、満を持して出版された待望のシーズン2的な位置づけになるのが、本作『てつたん!』だ。この発表に至るまでの、ウィーン学団なる徒党を組んで物議をかもした一部ファンの騒動、制作・ウィトゲンスタジオの終焉など、数々の波乱を乗り越えての出版だった。そんな本作は、クールでスパイシーだった前作とは一線を画し、日常系とさえ言えるほど肩の力が抜けている。しかしその脱力から生み出されるのは、むしろ前作のファンを裏切るような破壊的思索だ。2020年、リマスターで再登場。2021/02/19
双海(ふたみ)
4
もっとも信頼のおけるテキストである最新第4版の版権を得たという。鬼界氏は、『哲学探究』というテキストが、どのような構造になり、何をめざしているのか、日本語で明確にわかるよう、特に版権所有者の許可を得て、見出しや解説等を、十分に入れている。といっても私にはちょっと手に負えないのだが・・・笑2025/06/29
土曜の朝
4
斉一な『論考』に対して、『探究』は雑多という表現がしっくりくる。日常言語を様々なアスペクトから写し取った風景スケッチである。そしてそのスケッチは我々の日常にも通ずる。例えば、ChatGPTは言葉の意味や意図を理解しているように思える。しかし、これは我々の言語に対する誤解から生じている。実際には大量のテキストデータから言葉の使用パターンを解析して自然な応答を生成しているに過ぎない。しかしそれでも我々とChatGPTの言語ゲームは問題なく成り立つ。語の意味とはその使用である、を立証する事例ではないか。2023/06/11
ポルターガイスト
4
全体の雰囲気をつかむ程度に読んだ。読んだうちに入らないので再読する。感覚だけで言うと,ウィトゲンシュタインの問いや議論の方向性はとても好き。彼の本を読むと「一周回ってマイルドヤンキーの生き方こそが正しいと確信するようになった陰キャがひたすら理屈こね上げてヤンキーになろうとする物語」という感じがいつもする。それがいい。今作は『論理哲学論考』の反駁を目的としていると言われるし,実際,対照的な箇所は目立つが,個人的には『論考』の(ヤンキー的な)方向性をある意味で徹底した結果が『探究』なのではないかと感じました。2022/11/06
-

- 洋書
- NEFERTITI