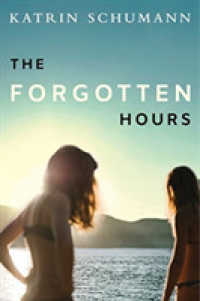- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
まさに平成が始まろうとしていた頃のこと、政治シーンのあちこちで「改革」の二文字が見られるようになった。以来30年、日本の統治システムは改革の名のもと、静かに、しかし激しく変貌を遂げてきた。選挙制度、行政、日銀・大蔵省、司法制度、地方分権……現在の政治を作り出した壮大な理念とその帰結を読み解く。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kuroma831
22
日本を代表する比較政治学者である待鳥聡史による1990年代からの15年に及ぶ政治改革を30年後の今として振り返り評価する。小選挙区比例代表並立制を導入した選挙制度改革が印象深いが、省庁再編を進めた行政改革、日本銀行・大蔵省改革、司法制度改革、地方分権改革といった公共部門の諸領域に及ぶ改革を総覧する。体制内での制度変革や合理化を目指す「近代主義右派」、政策アイデアの定着過程を「土着化」という概念で分析する。待鳥先生は大著「首相政治の制度分析」で高い評価を受けており、まさにその帰結を振り返る形になる。2025/11/04
俊介
18
政治改革に明け暮れた平成。政治家もマスコミも二言目には「改革、改革」言ってた気がする。自分としてはよく意味も分からず眺めてたけど、本書で、一連の改革がどういう意味を持ってたのか振り返るいい機会になった。衆議院選挙は小選挙区制になり、大蔵省は財務省になり、裁判員制度も出来た(小泉改革にはあまり触れない)。とにかく幅広いので、ひとつの評価軸で測るのは難しいとは思うが、著者としては『近代主義右派』の流れが背景にあるという見立てだ。その是非はともかく、平成の改革をここまで綺麗にまとめた本はあまり無いのでは。2020/11/10
かんがく
14
平成初期の「政治改革」について端的にまとまっている良書。近代主義(理想)と土着化(現実)をキーワードに、選挙・行政・日銀・司法・地方分権などの改革がどのような形で進んでいったかが丁寧に述べられている。一般的な誤解を冷静に突き返していく書き方も好印象。2021/02/23
武井 康則
14
1989年天皇が崩御し平成が始まる。リクルート事件、ベルリンの壁崩壊、バブルの崩壊。もはや戦後の仕組みでは太刀打ちできない。政治家の腐敗をなくし、市民に身近な政治を。選挙制度改革、行政改革、日本銀行・大蔵省改革、司法制度改革、地方分権改革と公共部門と呼ばれる領域の大部分で立て続けに改革が行われた。国民や官僚、政治家、マスコミの思惑が入り乱れ、方向が変わったり、思惑が外れたり。本書はその結果は評価せず、各改革の歴史に終始する。それは平成の歴史とも重なる。今の日本がなぜこうなのか、よくわかるもう一つの平成史。2020/10/01
msykst
13
面白かった。90年代からの一連の政治改革(行政改革/日銀大蔵省改革/司法制度改革/地方分権改革)についての本はこれまでも読んだ事があったけど、本書は「土着化」という概念を元にそれらを包括的に分析する。まず一連の改革の根底には、著者が「近代主義右派」と名付ける理念が共通してあると。しかし、政策化し現場に落とし込むまでの間には「土着化」というプロセスがあり、それによって理念とのズレが生じていったのではないか、という事を各論分析で示す。プロセスと結果の問題点は示しつつも、改革自体の意義と必要性は強調されている。2020/10/05
-
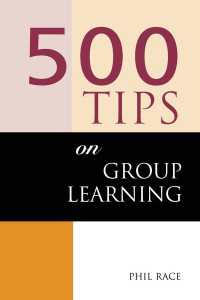
- 洋書電子書籍
- 500 Tips on Group L…