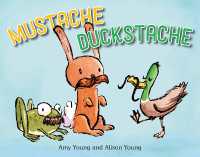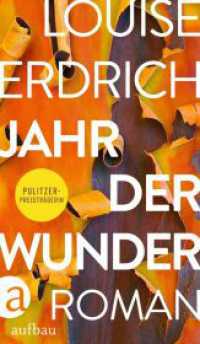内容説明
イソクラテスの思想の真髄
「善き言論」は「善き思慮」のしるし
古代ギリシアの教養理念に一大潮流を形成したイソクラテス。プラトンらが教養の原理に数理諸学や哲学を置いたのに対し、彼は弁論・修辞学を対置し、教育を実践した。やがてイソクラテスを源泉とする修辞学的教養はローマ、ルネサンスと受け継がれ、遠く近世にまで多大な影響を及ぼすことになる。イソクラテスの理想と教育を生き生きと描いた好著。
目次
1.序の章
2.イソクラテスの生涯
3.イソクラテスの学校
4.イソクラテスの教育
5.イソクラテスの教養理念
6.間奏の章――イソクラテスとプラトン――
7.イソクラテス学校とアカデメイア
8.イソクラテスの伝統――キケロから近代まで――
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
有沢翔治@文芸同人誌配布中
13
哲学者が建てた学校といえばアカデメイアやリュケイオンが思い浮かぶかもしれません。しかし、このイソクラテスもまた学校を開いていました。イソクラテスの学校では、修辞学を教えいましたが、師のゴルギアスとは違い、詭弁で煙に巻く術ではありません。むしろ修辞学や弁論術を通して、自分を磨く術だったのです。この修辞学はアリストテレスに渡り、キケロ、ペトラルカに受け継がれていくことになります。http://blog.livedoor.jp/shoji_arisawa/archives/51502700.html2018/12/31
iwasabi47
6
プラトンとイソクラテスの類似と差異。エピスメーテーと(健全な)ドクサ。プラトン対話編の同時代テクストの錯綜。書くことと語ること。アルキダマス『ソフィストについて』(納富信留『ソフィストとは誰かに』に訳掲載)2020/09/05
えふのらん
5
異端の修辞学者イソクラスを軸にしたアテナイの知的状況の分析。同著者によるプラトンの学園に対応しており本書は比較対象にアカデメイアを設定している。アカデメイアと対立していた何てことは読むまでもなくわかりきったことなのだが、意外にもプラトンの師ソクラテスにイソクラテスは憧れていたらしい。彼は修辞を施すにしても最終的には善を目指すことが必要で、プラトンと対立はしていたものの善美の事柄の必要を自覚していた。むしろ師であったゴルギアスらの即興的、やり込めるだけのレトリックには一定の距離をあけていたのだという2022/11/25
buuupuuu
5
人間らしさの本質が「相互に説得しあい、われわれの求めるものを明らかにする能力」にあると考えたイソクラテスは、弁論・修辞学を中心にして教養を構想したという。この教養は、有限な存在である人間が、変化する状況の中で蓋然的な判断を下し、行動するのを助ける実践的なものとされ、数学に範を取り、理論的・絶対的な知識を志向したプラトンと対立する。名指しされていなくとも、各々のテキストに互いについての批判と考えられる箇所が確認できるのが面白い。今キケロを読んでいるので、彼の属する伝統の源流を知れてよかった。2021/08/05
サアベドラ
3
ヨーロッパには教養が2種類ある。プラトン、アリストテレスに代表される哲学的教養とソフィストからイソクラテス、キケロ、ペトラルカへいたる修辞学的教養である。前者はいいとして、後者は非常に大雑把に言うと「修辞的で、論理的で、美しい文章を書くことが人格の陶冶につながる」という考え方である。欧文には分詞や複文を多用したやたらと長い文があるが、それがキケロ以降の修辞学的伝統なのである。要するに、受験英語が嫌に長ったらしくて回りくどいのはこのイソクラテスが原因なのだ。全国の受験生よ、イソクラテスを糾弾せよ。2009/08/22
-
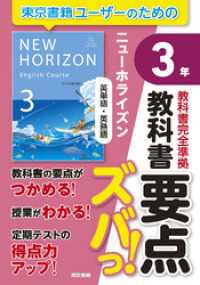
- 電子書籍
- 教科書要点ズバっ! ニューホライズン …