内容説明
大学新入生しょくんへ、そして“じぶんって考えるのヘタかも?”と思ってる大人のみなさんへ。累計26万部突破『新版 論文の教室』著者による、思考のトレーニング本がここに誕生。
「演繹」「帰納」をいっさい使わず身近な例を豊富にまじえ、まずは論理的思考の本質を柔らかく説く。でも、さまざまな偏見や思考の飛躍によって、論理の筋道は曲がりくねってしまう。ならば、“じょうずに考える”ためには、どんな装置を使って、何をどのように勉強すればいいのか?
語彙力強化の秘伝から、じぶんの考えを効率的に伝えるための文章設計術、相手の考えをきちんと理解するためのクリティカル・リーディング、相手といっしょに考えるためのディベート術まで、ユーモア&論理エキスたっぷりの戸田山節で講義。“考える”ためのすべてを網羅した「知の教典」、練習問題42問も付いた決定版! “じょうずに考える”ためには、やっぱり考えてみないとダメなんだ。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
esop
63
論理的に考える、書く、話すとは、つねに自分の思考・主張にできるだけ強いサポートを与えることに気を配りながら、思考や文をつなげていくことである/だからキミは使える言葉を増やさなければならない/語彙ノートをつくる/レジュメや要約はたんに分量を少なくすることじゃないーーもとの文の論証の構造を再構成して明示したもの/主張を証拠でサポートする型の文章(サポ文)を書けることは、民主主義社会に暮らすかぎり、誰にとっても重要である2024/05/16
のっち
17
☆☆☆☆★ 若者向け語り口調でとても読みやすいが、内容は大変深い。我々は自身の知る言葉の範囲内において思考が可能である。したがって、語彙力を増やすことは思考の枠組を拡張する上で必要である。語彙力の豊富な人とそうでない人では、同じ体験をしてもそこから得る洞察に差が生じる。また学びについても同じことが言える。学問はこれまでの人類の知の集積であり、何も頭の良い人のためにあるわけではない。学問をすることにより思考の手段の幅が拡がるという点において、我々一般人にこそ学ぶ意義がある。2023/07/25
三井剛一
13
論理的思考から文章設計、クリティカルリーディング、バイアス等、思考・学問について専門用語を使わず、まとめらている。著者独特の文体とユーモアで手取り足取り先導してもらった。より良く生きる上で欠かせないことがつまっていた。自分のアホさ加減と向き合い続ける。2024/11/26
羊山羊
11
巷のビジネス本を読む前に、まずクリアしておく必要のある本が本著ではないか、と思う。思考の教室の名の通り、論理的思考が踏むべきステップを丁寧に教えてくれる。仮説思考とか推論とか、そういったビジネス書がイマイチ腑に落ちない場合は、本番が述べている範囲の事がしっかり身についていないかもしれない。第7章までの内容は、ビジネス本初学者には必読の内容だ。理論、というのが、いかにして成り立っているのかがよく分かる。私自身、とっても反省する所の多かった1冊。→2025/05/19
左手爆弾
9
なんというか、名著である。いや、教科書として書かれているので、名著と呼ぶのは少し違うのかもしれないが。「考えるとはどういうことか」からはじまって、「上手に考えること」へと進んでいく。その際に、別に学者になるわけじゃなくても、幸せになるためにこそ、懐疑主義や独断主義に陥らないように考えるためにはどうすればよいかという問題設定があるのがよい。練習問題も豊富なので、教育的効果もある。ただ、この本を手に取る時点で、それなりにうまく考えられてるのではないかという気もする(そこはどうしようもないか)。2022/09/09
-
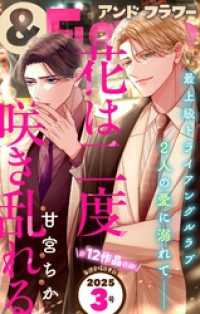
- 電子書籍
- &フラワー 2025年3号 &フラワー
-

- 電子書籍
- アリスの国の殺人<新装版> 徳間文庫
-

- 電子書籍
- すばらしき新世界(フルカラー) 8 ズ…
-
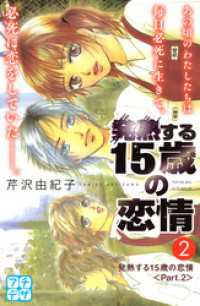
- 電子書籍
- 発熱する15歳の恋情 プチデザ(2)
-
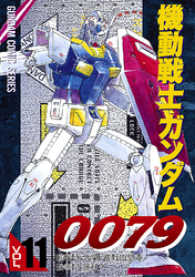
- 電子書籍
- 機動戦士ガンダム0079 〈11〉 電…




