内容説明
※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
著者は、金沢大学工学部名誉教授であり、現・日本コーヒー文化学会の会長。1999年から全国で唯一の文部科学省認定の授業「コーヒーの世界」を金沢大学で開講した。本書は、コーヒーを工学の視点から、焙煎、抽出法、その香りと色、その品質評価と「好み」の分析、ブレンドについて、コーヒーと水とミルク、缶コーヒーについて分析する。コーヒーの生豆を焙煎すると、コーヒー豆の内部がハチの巣のような構造=ハニカム構造になっていることを中核にし、本書のコーヒー学は展開される。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mujimaru51
7
コーヒーに化学的な面からアプローチした本であり、コーヒー自体の生豆種類、焙煎の種類、抽出過程について初心者から一歩踏み込んな方向けに解り易く解説されています。これ以外にも焙煎や抽出について書かれている本は多くありますが、本書の特徴はあくまでも『もっと知りたいコーヒー学』と銘打っている通り、入門書を終えてもう少しその先が知りたい方への化学工学面からの知識を補完するスタンスをとっています。こシステム焙煎工学について、または抽出技術について知りたい方向けの数少ない専門書だと思います。2016/02/23
ももとり
3
科学的な手法と言っていいのか怪しいところが多々あった(工学屋…?という印象)のと、分析対象が広範囲に広がりすぎて月並みなことしか言えてない点が微妙。淹れ方の比較でプレス完全無視してるのはどうなんだ。しかし自分の興味があるところ、かつ信用できそうな部分の記述は面白かった。2014/11/14
luna piena
2
今まで自分の感覚で信じてやってきたことの方程式が明確になった。そして、いつもと違う視点からもコーヒーを考えられた。やっぱりこの人もあたしも、コーヒーが大好きなんだな。2011/02/04
中山りの
1
図書館本。 焙煎された豆はハニカム構造をしている。その組織内の空洞は、焙煎が進むにつれて大きくなる。その結果、空洞内の表面積も大きくなってくる。 豆は焙煎時、センターカットの部分から火が通ることで中心部も焼ける。 また、焙煎によってクロロゲン酸の含有量は減少する。 などなど、勉強になったことも多い。科学的な分析も有用だろう。しかし結局、多くのひとはあんまり小難しいことを考えずに雰囲気で美味しく感じている。 どんな姿勢であろうと、美味しいものを美味しくいただけるのがいちばんだ。2020/09/10
-
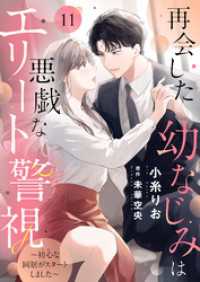
- 電子書籍
- 再会した幼なじみは悪戯なエリート警視~…
-
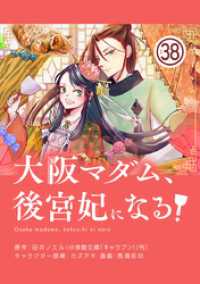
- 電子書籍
- 大阪マダム、後宮妃になる!【単話】(3…
-

- 電子書籍
- 龍の棲む池【タテヨミ】第13話 pic…
-
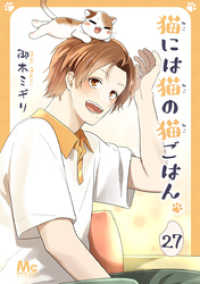
- 電子書籍
- 猫には猫の猫ごはん。 27 マーガレッ…
-

- 電子書籍
- 青い鳥飛ばそ!(分冊版) 【第6話】




