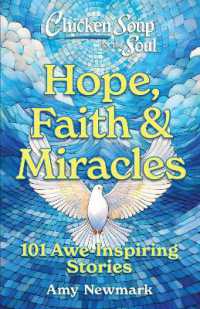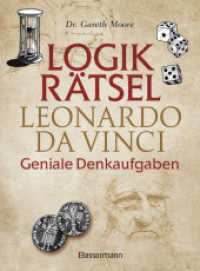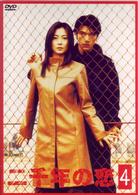- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
現代社会の礎は、信長や秀吉ではなく、戦国北条家が築いていた。印判状、目安制などを切り口に、税・裁判制度、判子文化のはじまりを大河『真田丸』の時代考証者が表現。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
71
早雲以来の後北条氏が百年余にわたり構築してきた統治システムが、江戸時代を経て今日の国家体制の基盤になっていたとは。天下統一という政治レベルは織豊時代の功績だが、納税や公平な裁判を行うための目安制、国家意識形成に公共事業など「国民のための行政」は北条氏のやり方が淵源と知ればれ歴史のイメージが刷新されてしまう。しかも公文書押印を北条氏が始めたことは、近代日本を支配したハンコ行政の開祖といえる。民を富ませようとした北条氏に対し、一度も反乱が起きなかったのも当然か。支配ではなく民政こそ政治の要だと納得させられる。2021/07/04
ようはん
23
戦国時代は武将の動向や戦に注目しがちで戦国大名の領国統治に関してはあまり知らなかった。どの戦国大名も領国経営には腐心していたとは思うが、特に後北条氏は印判に記された「禄寿応穏」というスローガンの通りに領民の安寧を第一に考えており、それが後北条氏の領国経営システムの先進性を創り出していったと言える。2022/10/19
鯖
22
毎度おなじみ黒田先生の北条氏の行政システムに焦点を当てた本。目安箱で知られる「目安」とはそもそも訴状を指し、集落が直接幕府や戦国大名に訴訟を起こすことはできず、領主を通じて訴訟するのが原則だった。しかし北条氏が集落からの直接訴訟を可能としたのが目安であり、目安制が代官の不正、ひいては村落同士の諍いにおいても訴訟制度として機能し、自力救済から解放されたとの指摘が興味深かった。2021/01/31
組織液
19
いやぁ面白かったです!北条家が構築した行政制度や統治方法を、7つの項目に分けて前近代、そして現代と対比しています。薄いし黒田先生自身も一般向けに書いたと述べられていましたが、一番最初の章から「日下」とか書いてるんでほんとに一般向けかこれ…?とは思いました() まぁ内容自体は特別難しい訳ではないですね。ただ中世の行政などそこら辺の話はわからないところがかなり多いので(本書にも研究者であっても認識されていないとか書いてましたし)丹念に勉強していきたいです。2021/06/01
フランソワーズ
13
対外戦争だけでなく、天変地異や飢饉といったものに絶えず左右されていた戦国時代。戦国大名国家は列島史上初の統治権力であり、それ以前の権力と異なり、「村の成り立ち」の維持・保証する責務があった。そのための政策として、判子行政や目安制、減税・増税・納税方法を含む税制改革をきめ細やかに行わなければ、領国は保てなかった。その好例が、残存史料が豊富な北条家。ここから様々なことが理解でき、それが実は現代にまで繋がっていることに驚かされました。→2021/09/08