内容説明
ペットと家族同然に暮らしている人はもちろん、テレビやネットで目にする動物の映像を見てかわいらしく感じたり、絶滅が危惧される動物や虐待される動物がいることを知って胸を痛めたりする私たちは、動物を保護するのはよいことだと信じて疑いません。しかし、それはそんなに単純なことでしょうか――本書は、このシンプルな疑問から出発します。
子供の頃、挿絵が入った『シートン動物記』をワクワクしながらめくった記憶をもっている人でも、作者のアーネスト・T・シートン(1860-1946年)がどんな人なのかを知らない場合が多いでしょう。イギリスで生まれ、アメリカに移住してベストセラー作家となったシートンは、アメリカではやがて時代遅れとされ、「非科学的」という烙印を捺されることになります。そうして忘れられたシートンの著作は、しかし昭和10年代の日本で広く読まれるようになり、今日に至るまで多くの子供が手にする「良書」の地位を確立しました。その背景には、シートンを積極的に紹介した平岩米吉(1897-1986年)という存在があります。
こうして育まれた日本人の動物観は、20世紀も末を迎えた1996年、テレビの人気番組の取材で訪れていたロシアのカムチャツカ半島南部にあるクリル湖畔でヒグマに襲われて死去した星野道夫(1952-96年)を通して鮮明に浮かび上がります。この異端の写真家は、アラスカの狩猟先住民に魅了され、現地で暮らす中で、西洋的でも非西洋的でもない自然観や動物観を身につけました。それは日本人にも内在している「都市」の感性が動物観にも影を落としていることを明らかにします。
本書は、これらの考察を踏まえ、2009年に公開され、世界中で賛否両論を引き起こした映画『ザ・コーヴ』について考えます。和歌山県太地町で行われてきた伝統的なイルカ漁を告発するこのドキュメンタリーは、イルカを高度な知性をもつ生き物として特権視する運動と深く関わるものです。その源に立つ科学者ジョン・カニンガム・リリィ(1915-2001年)の変遷をたどるとき、この映画には異文化衝突だけでなく、近代の「動物保護」には進歩主義的な世界観や、さらには西洋的な人種階層のイデオロギーが反映されていることが明らかになります。
本書は、動物を大切にするというふるまいが、実は多くの事情や意図が絡まり合った歴史を背負っていることを具体的な例を通して示します。一度立ち止まって考えてみるとき、本当の意味で動物を大切にするとはどういうことかが見えてくるでしょう。
[本書の内容]
はじめに
序 論――東西二元論を越えて
第I章 忘れられた作家シートン
第II章 ある写真家の死――写真家・星野道夫の軌跡
第III章 快楽としての動物保護――イルカをめぐる現代的神話
おわりに
目次
はじめに
序 論――東西二元論を越えて
第I章 忘れられた作家シートン
一 『動物記』とアメリカ
二 「人種再生」のビジョン
三 日本科学の精神と『動物記』
四 孤高の人々――平岩とシートンの動物観
第II章 ある写真家の死――写真家・星野道夫の軌跡
一 Michioの死とその周辺
二 原野をめぐる言説
三 星野が見た「アラスカ」
第III章 快楽としての動物保護――イルカをめぐる現代的神話
一 なぜイルカなのか
二 イメージの系譜学
三 人種階層と動物保護
四 宇宙を泳ぐイルカ
五 再び『ザ・コーヴ』へ
おわりに
注
文献一覧
初出一覧
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ベル@bell-zou
Sakie
まえぞう
さまい
kenitirokikuti
-
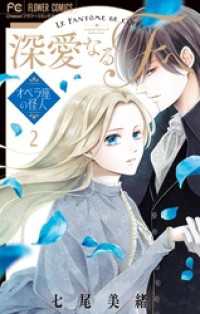
- 電子書籍
- 深愛なるFへ オペラ座の怪人(2) フ…
-

- 電子書籍
- 恋愛チェリーピンク2021年1月号 恋…







