内容説明
「894年遣唐使廃止」は日本を変える出来事ではなかった。
列島を取り巻く大海原をたくましく乗り越え、「外」と日本を繋ぎ続ける人たちがいた―
利を求め海を闊歩する海商たちと、
彼らの助けを得て、最新の知識を求めて大陸へ渡ろうとする僧侶たち。
多くの記録を史料に残した僧たちの足跡を辿ることで、海域交流の実相に迫り、歴史世界としての東シナ海を描き出す!
[本書の内容]
序章 中世日本と東シナ海
第1章 「遣唐使以後」へ
最後の遣唐使、出発
海商の登場
「遣唐使以後」の入唐僧たち
第2章 古代から中世へ
平安王朝の対外政策
帰国しなかった僧たち
密航僧の出現
第3章 大陸へ殺到する僧たち
「中世」の始まり
日宋仏教界をつないだ人脈―入宋僧円爾
日元関係の波紋と仏教交流―入元僧龍山徳見
第4章 「遣明使の時代」へ
混乱の海、統制の海
仏教交流の変質
補章 遣明使の後に続いたもの
※本書は2010年に講談社選書メチエより刊行された『 選書日本中世史4 僧侶と海商たちの東シナ海』を原本とし、改訂を加え補章を付して文庫化したものです。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
MUNEKAZ
15
894年の遣唐使停止から明初までを中心に、東シナ海を舞台とした海域史。遣唐使の停止で大陸との交流が一切途絶えたわけでもなければ、倭寇が跋扈する混乱期に入ったのでもない。海商たちの活躍と国家統制の緩和により、それまで以上に日本と海外との交流があったことを描いている。著者は中国に渡った多くの日本僧たちに注目することで、この従来あまり注目されることの少なかった豊かな海外交流の歴史を紹介しており、興味深い点が多い。元寇や明の海禁政策に翻弄されながらも、留学への情熱を失わなかった僧侶たちの姿は眩しいものがある。2021/03/17
nagoyan
11
優。日中関係史を渡唐・宋・元・明僧らの記録から復元。遣唐使の間隔が30年となっても、遣唐使船に乗らず唐に残った円仁。実は既に新羅海商による日羅唐のルートがあった。新羅政変に伴い新羅ルートに代わって東シナ海ルート。唐海商活躍へ。遣唐使後も日本朝廷は対外交通を大宰府で管理。財政難が国家管理を空洞化(成尋の密航)。渡宋のブームに。元時代、軍事的緊張により一時往来が減少するもの大勢は貿易の振興と自由な往来。明の政治情勢により状況は一変。渡来僧の時代に。キリスト教布教も「渡来僧」の一つ。意外に旺盛な対外交流。2020/10/31
qwer0987
7
歴史にはいろいろな側面や切り口があると教えてくれる。東シナ海の通航を巡る歴史なのだが、知らないことばかりだった。むかしの僧侶たちは大陸の仏教文化に憧れ多く海を渡ったようだ。遣唐使廃止後も僧は渡海していたことや、そんな時代でもある程度中央が制御していた点も驚く。そして海を渡る上では、海商たちの船の存在が大きかったらしい。だけどそれも元寇や洪武帝の政策など当時の政治状況に左右されている。けど密航してでも渡海しようという僧たちもあり、その情熱には脱帽する。多くが見向きもしない周縁部の歴史と魅力を堪能できた次第だ2022/04/29
積読0415
7
「しないことを決めた」ということを、わざわざ覚えさせるのが894年の遣唐使廃止だが、本書はその前の838年の承和度遣唐使をスタートとし、そこからの東シナ海の交流の話が進む。この段階で、昔聞いた「遣唐使が無くなったから日本独自の国風文化が生まれた」式の説明が否定される。昔習った歴史が「更新」されている感覚である。2021/04/08
イツシノコヲリ
2
とりあえず2章まで。古代における遣唐使であるが、最初は次の遣唐使まで帰ってこれないため、留学を取りやめることも多くあったが、円仁の時代になって新羅海商を利用することにより、帰りやすくなり、円載のように70歳まで唐に居座る僧も出てきた。密航する僧は意外に少なく、平安時代でも対外政策はしっかりと取られていたと感じた。2025/11/09
-
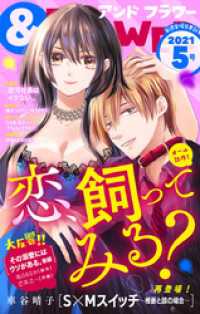
- 電子書籍
- &フラワー 2021年5号 &フラワー
-

- 電子書籍
- おうし座の男 - 12星座別★男の取扱…






