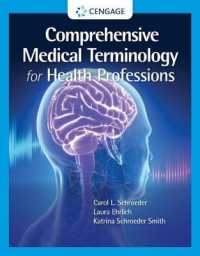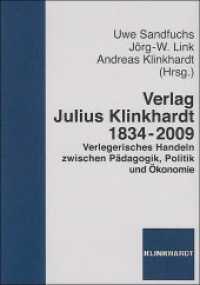内容説明
人が人にさわる/ふれるとき、そこにはどんな交流が生まれるのか。
介助、子育て、教育、性愛、看取りなど、さまざまな関わりの場面で、
コミュニケーションは単なる情報伝達の領域を超えて相互的に豊かに深まる。
ときに侵襲的、一方向的な「さわる」から、意志や衝動の確認、共鳴・信頼を生み出す沃野の通路となる「ふれる」へ。
相手を知るために伸ばされる手は、表面から内部へと浸透しつつ、相手との境界、自分の体の輪郭を曖昧にし、新たな関係を呼び覚ます。
目ではなく触覚が生み出す、人間同士の関係の創造的可能性を探る。
目次
序
第1章 倫理:ほんとうの教育/フレーベルの恩物/「倫理一般」は存在しない 他
第2章 触覚:低級感覚としての触覚/内部に入り込む触覚 他
第3章 信頼:安心と信頼は違う/「ふれられる」とは主導権を手渡すこと 他
第4章 コミュニケーション:記号的メディア/物理的メディア/伝達モード/生成モード 他
第5章 共鳴:遊びから生まれる「共鳴」/「伝える」ではなく「伝わっていく」 他
終 章 不埒な手:介助とセックス/不道徳だからこそ倫理的でありうる 他
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
けんとまん1007
115
「さわる」と「ふれる」をメインに、その違いについての考察が素晴らしく、興味深い。確かに、書かれているとおり、似て非なるもののように思う。ここのありようが違うと思うし、その距離感の違いが大きい。五感の中の触覚のありよう。その中でも、手が占める意味合いの大きさ。ブラインドランナーの事例が、わかりやすく伝わるものが大きかった。人間の奥深さを感じた。「ふれる」は「ふれあい」に通じるのは、なるほどと。2020/12/17
アキ
96
手の歴史とは触覚がもたらす昔の記憶。人にさわるとは信頼がなければ不埒になる。道徳を相対化する不道徳性。ケアの現場では状況の複雑さに向き合い、ふれるという創造的な倫理が求められる。西洋哲学では視覚や聴覚に比べ触覚は劣った感覚とされる。触覚を距離ゼロ、持続性、対称性の3つのポイントから考える。それは対象の内部にはいりこむもの。さわるは伝達、ふれるは生成モードのコミュニケーション。目の見えない人と伴走者間のロープを介する共鳴の言葉の不要な一体感。手拭いを使っての柔道観戦。人間同士の関係の新たな視点を触覚がひらく2021/03/09
どんぐり
90
目の見えない人や、どもる人など障害者の身体論をテーマに研究している著者の本。今回は「さわる/ふれる」触覚を取り上げ、手をとおした人間関係を論じている。「さわる」が一方的で、「ふれる」が相互的関係。介護や看護の現場で働く人であれば、「さわる/ふれる」身体的接触なくしては成立しないが、ふつうの人が生身の人間にさわる/ふれる機会は、そう多くはない。→2021/03/12
ネギっ子gen
77
【一方向的な「さわる」から、共鳴・信頼の通路となる「ふれる」へ】「touth」の日本語訳は「さわる」と「ふれる」だが、微妙にニュアンスが異なる。「逆鱗にふれる」とか「神経にさわる」とかいう表現。触覚の最大のポイントは、それが親密さにも、暴力にも通じているということ。触感は触り方次第なのか。<触覚を担うのは手だけではありませんが、人間関係という意味で主要な役割を果たすのはやはり手です。さまざまな場面における手の働きに注目しながら、そこにある触覚ならではの関わりのかたちを明らかにする>。これが本書のテーマ。⇒2022/11/27
shikashika555
54
「さわる」と「ふれる」はどう違うのか。 二者の身体接触の境界にその概念はある。 普段は意識に上りにくい業務的な接触を、いかに丁寧に互いの不快が少ない状態で行うかは個人的な課題として考え続けているが、本書によってさらに考えを深めることが出来た。 考えさせられたのは、身体接触をする方 受ける方 共に「不確実性」というリスクを背負っているということ。 これは わかっているようでわかっていない。 試験には答えられるが、いざ実際の接触時には コロリと頭から抜け落ちてしまいやすいことではないか。2020/12/11