内容説明
阪急創業者・小林一三は、「政治中心」の東京に対して、大阪を「民衆の大都会」と呼んだ。
ターミナル・デパート、高級住宅地……国鉄に対抗し「官」からの独立を志向する関西私鉄は、沿線に市民文化を花開かせ、「民衆の都」大阪は東京を凌駕する発展を見せた。
だが、大正から昭和への転換、昭和天皇行幸を機に、街は次第に「帝都」へと変質してゆく―。
権力の装置=「国鉄」と関西私鉄との葛藤を通し、「都市の自由」の可能性とその挫折を描く、原武史の代表作。
第20回(1998年) サントリー学芸賞(社会・風俗部門)受賞。
[解説(鹿島茂)より]
「横軸としての鉄道に、縦軸としての天皇が交差することによって、思考の座標軸が形成され、二つのパラメーターが思考の軌跡をさまざまに描き出す」
[本書の内容]
はじめに―昭和大礼の光景
第一章 私鉄という文化装置
「帝国」と「王国」
『細雪』から
関東私鉄と関西私鉄
第二章 「私鉄王国」の黎明
第五回内国勧業博覧会
法の抜け穴
二つの風土
第三章 「阪急文化圏」の成立
往来ふ汽車を下に見て―小林一三という人物
民衆の都
沿線文化の確立
反官思想の結実―阪急デパート
第四章 昭和天皇の登場
「大大阪」の誕生
昭和大礼と都市空間の変容
官民協力奮励セヨ―一九二九年の行幸
第五章 阪急クロス問題
「官」の巻き返し
逆風
小林一三、社長を辞任す
第六章 「帝都」としての大阪
大阪市民たるもの
天皇のまなざし
一生一代の御奉公
おわりに―「紀元二千六百年」の光景
解説=鹿島茂
※本書の原本は1998年に講談社選書メチエより刊行されました。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
まーくん
無重力蜜柑
かんがく
さとうしん
おっとー
-
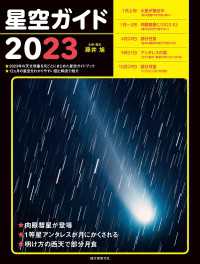
- 電子書籍
- 星空ガイド2023
-

- 電子書籍
- 宇宙が味方の見方道 - こんなふうにと…
-

- 電子書籍
- 私の夫は冷凍庫に眠っている【単話】(1…
-
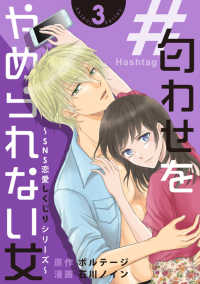
- 電子書籍
- #匂わせをやめられない女~SNS恋愛し…
-

- 電子書籍
- アオイホノオ(18) ゲッサン少年サン…




