内容説明
平安時代後期から戦国時代の終わりまで、中世をになった特徴的存在が武士団です。
「土」と結びついたイエ支配権の強力さと独立性、生活の実際と意識のあり方、10世紀初頭の武士団の実体と鎌倉武士団への発展の過程、「板碑」が語る武士団の歴史、安芸国の小早川氏に見る鎌倉的武士団から南北朝・室町的武士団への変貌の経過と武士団の支配下の荘園の様相、北陸の雄たる朝倉氏の城下町、越前一乗谷の考古学的発掘の成果をとり入れた戦国武士団の一面。そして中世から近世へと移りゆくなかで武士団が喪失した「自立性」への惜しみない哀悼。
本書は、日本中世史の泰斗が「中世武士団」という社会集団の実態と特色、そして中世社会の構造を、歴史書、文学作品、碑文、考古学資料を駆使し鮮やかに描き出し、高い評価を受け続けている作品です。30年以上前の著作ではありますが、学生や研究者にとっては今なお必読書であり、一般読者層にとっては最良の日本中世史入門といえる名著です。
〔原本/1974年、小学館「日本の歴史」12巻『中世武士団』〕
※本書の原本は1974年、小学館より「日本の歴史」第十二巻『中世武士団』として刊行されました。講談社学術文庫収録にあたっては、同社より1990年に刊行された「文庫判 日本史の社会集団」第三巻『中世武士団』を底本とし、2005年に山川出版社から刊行された「石井進の世界」第二巻『中世武士団』を参照しました。
【目次より】
中世武士団の性格と特色――はじめに
曾我物語の世界
敵討とその周辺
「兵」の館をたずねて
「兵」から鎌倉武士団へ
板碑は語る
武士団とは何か
小早川の流れ(一)――鎌倉時代の歩み
小早川の流れ(二)――南北朝・室町時代の武士団
埋もれていた戦国の城下町――朝倉氏の一乗谷
失われたもの、発見されるもの――おわりに
目次
中世武士団の性格と特色――はじめに
曾我物語の世界
敵討とその周辺
「兵」の館をたずねて
「兵」から鎌倉武士団へ
板碑は語る
武士団とは何か
小早川の流れ(一)――鎌倉時代の歩み
小早川の流れ(二)――南北朝・室町時代の武士団
埋もれていた戦国の城下町――朝倉氏の一乗谷
失われたもの、発見されるもの――おわりに
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
翔亀
翠埜もぐら
fseigojp
のれん
qwer0987
-

- 電子書籍
- 悪役魔女になるなんて聞いてない【タテヨ…
-
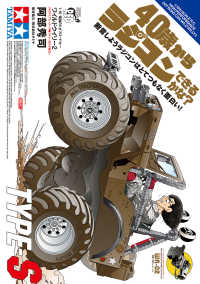
- 電子書籍
- 40歳からラジコンできるかな? 断言し…
-
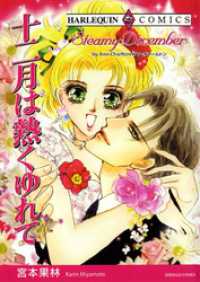
- 電子書籍
- 十二月は熱くゆれて【分冊】 1巻 ハー…
-
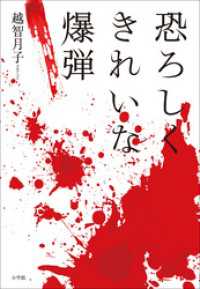
- 電子書籍
- 恐ろしくきれいな爆弾
-
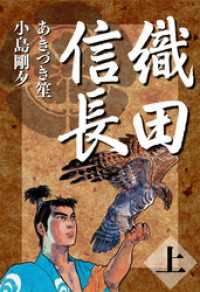
- 電子書籍
- 織田信長 上 小池書院




