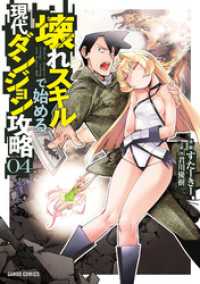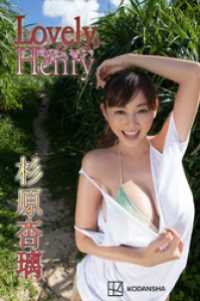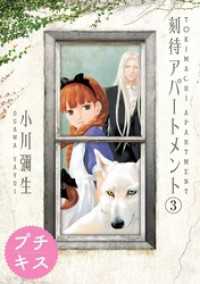内容説明
古代スラヴ語とは、西暦9世紀の後半から11世紀末にかけて、当時のスラヴ人が文章語として用いた言葉。自分たちの言葉を教会の典礼言語として整えるためにグラゴール文字が作られ、そしてキリル文字へと変わっていった過程をたどります。さらに、スラヴの言語は、歴史と共にどのように変化していったのか。なぜ、キリル文字を使う言語とラテン文字を使う言語に分かれているのか。言葉と文字の変遷から東欧の基礎的な成り立ちが見えてきます。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
へくとぱすかる
60
グラゴール文字への興味から。東欧の歴史の記述に重点が置かれているため、言語学・文字学にかかわるページは少ないが、千野栄一「スラヴ系文字の発展」(講座言語第5巻『世界の文字』所収)に簡略に紹介された、コンスタンチンとメトディ-の文字創作にいたる背景が、地理・歴史ともにくわしく述べられている。当時のビザンツ帝国とフランク王国の対立、キリスト教会の立場のちがいが、グラゴール文字、さらにはキリル文字を生んだと言えるだろう。兄弟の努力が灰燼に帰したのは初耳だったが、文字文化への影響は現代にまで生きているとも言える。2020/05/24
サアベドラ
29
古代教会スラヴ語(OCS)と、それが用いられた時代のスラヴ人を取り巻く国際情勢を平易に解説した本。2020年刊。著者は言語畑の人で歴史叙述は少々たどたどしい。古代教会スラヴ語は9世紀なかばにギリシア人聖職者によって作り出された典礼言語で、初期はグラゴール文字、後にキリル文字が用いられた。スラヴ人諸国家の浮き沈みと東西教会の綱引きに巻き込まれ、時に保護されたり時に弾圧されたり大変だったようだが、スラヴ民族の文化形成に多大な影響を与えたという。マニアックな内容だがかなり噛み砕いて書いてあるのでサラッと読める。2020/07/23
文公
20
『キリール文字の誕生 スラヴ文化の礎を築いた人たち』(原求作、上智大学出版、2014)よりも、スラヴ文字研究史、中世以降現代までの各スラヴ諸語におけるキリル文字の位置付けの変遷等にページを割いてあり、面白かった。スラヴ諸語の使用地域が広範囲且つそれらの歴史的な変遷を扱いながらも、各章の冒頭や結論部分でこれまでの著者の記述を簡単にまとめてあるので、頭の中で整理するのが容易だった。色々と気付きや発見があり、図書館から借りた本でなければ書き込んでいたのに。2020/07/25
MUNEKAZ
17
9世紀から11世紀にかけて、スラヴ人が使用した「古代スラヴ語」の変遷を描いた一冊。言語畑の人の著作なので、言語学的な話がメインかと思いきや、言語を通して東欧の、そしてスラヴ人の歴史を追う内容(言語的な話はコラムでちょこっと触れるだけ)。広くスラヴ語として共通の話し言葉を持っていたスラヴ人が、ビザンツ帝国やフランク王国との駆け引きの中で、古代スラブ語を獲得し、また政治的にも分裂していく様子がよくわかる。「文字」の持つ政治的な意味合いを考えさせられる内容で、ウクライナ戦争に揺れる今だからこそ興味深く読める。2022/08/29
yoneyama
16
興味深いスラヴ諸語の原型から形成、周辺諸族との交渉と移動の歴史などが述べられる208ページ。キリル文字の前にあってキリル文字形成の礎になったけど全く別のグラゴール文字のこと、古代スラヴ語はモラヴィア→ブルガリア→キエフ・ルーシ862年へと引き継がれたこと。文字、言語、種族そして宗教含む文化が、必ずしも一致しないので区別したり重ねたりして辿る必要がある。面白い。おそらく門外漢の入門レベル本なのかな。コラム多く読みやすし。8世紀〜10世紀なんて日本でもこのくらいなのか。いや、日本のほうがわかっているのか?2024/01/25