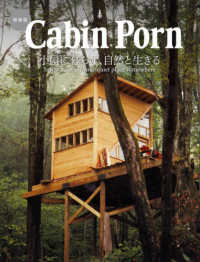- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
「9割近くは外出している」「不登校がきっかけは2割以下」「10年以上働いた後になることも」――。顕在化してからおよそ25年、かつては「青少年の一時的な現象」とされた引きこもりの内実は激変した。その数はいまや100万人を優に超え、問題も多様になり、従来のイメージでは捉えきれなくなっている。親は、本人は、社会は、何をすればいいのか。引きこもり支援で圧倒的な実績を誇るNPOの知見で示す最適解。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
GAKU
53
「9割近くは外出している」「不登校がきっかけは2割以下」「10年以上働いた後になることも」―。引きこもり内容は激変したと著者は述べています。それぞれ個々の事情は色々あると思いますが、この手の著書を読む度に感じるのですが、結局のところ親が生活の面倒を見ている。それではいつまでたっても引きこもりから抜け出さないのでは?まずは親が世間体とかを気にせずに、この著者が所属している支援団体等に相談し、早期に解決しようという姿勢が大事なのではと感じた。2020/09/27
mo
34
2年前に出た本だけど、ぼんやりとしか知らなかった引きこもりについて色々知ることができた。原因が多様化している引きこもりには、それぞれに合った多様な支援が必要なこと。子供を育てるのに親二人だけでは足りず、他者が必要なこと。これらは心に留めておきたいと思った。2022/09/05
どぶねずみ
30
引きこもりとはトイレ以外は部屋から全く出ないわけではなく、自分の買い物のために家を出たりすることはできる。最近よくきく8050という言葉もいつか9060になりうる。30年以上前から登校拒否とも言われていたが、言葉を変えて未だに解決策が見いだせず、高年齢化でより深刻だ。親離れ子離れが課題とも言える。厄介なのが親の思い込みで、相談はするくせに支援者の話を聞かない親は、ダークな部分は隠す。学生時代のイジメより職場の人間関係の精神ダメージの方が立ち直れないし、考え方を改めないと直接の解決にはならない難しい問題だ。2022/05/25
金吾
28
イメージの引きこもりとデータで解説された引きこもりの違いに驚きました。自分がステレオタイプで物事をみていたのだなあと感じます。引きこもりに対する家族の対処の部分が辛辣な部分も含めよく伝わりました。2025/06/04
おいしゃん
24
著者は、引きこもりを外の世界へ出す団体のメムバーだが、同業には暴力や力ずくで出させ問題になる団体も多いため、いかにそれらと違うか注意深く記されている。それらの見極めや、引きこもりを解消させるヒントも多い。2023/09/26
-
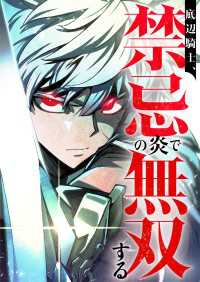
- 電子書籍
- 底辺騎士、禁忌の炎で無双する 21話 …