内容説明
当事者研究とは,自分と似た仲間との共同研究を通じて,等身大の〈わたし〉を発見すること,そんな自分を受け容れるものへと社会を変化させることを通じて,回復へと導く実践である.当事者研究の誕生の背景と方法論を紹介し,自閉スペクトラム症研究を例に,知識や支援法の共同創造が始まりつつある現状を報告する.
目次
はじめに
第1章 当事者研究の誕生
1-1 当事者研究を生んだ二つの潮流――当事者運動と依存症自助グループ
1-2 当事者運動――医学モデルから社会モデルへ
1-3 当事者運動が見逃したもの――見えにくい障害と公的空間の重要性
1-4 依存症自助グループ――言葉で公的空間を立ち上げる場所
1-5 依存症自助グループが見逃したもの――私的空間の重要性と薬物依存症者
第2章 回復の再定義――回復とは発見である
2-1 回復アプローチ
2-2 当事者研究における回復像
2-3 自己の物語の真理性
第3章 当事者研究の方法
3-1 通状況的なパターンの抽出と物語の統合
3-2 自己に関する知識と類似した他者の意義
第4章 発見――知識の共同創造
4-1 ASDについての教科書的な説明
4-2 ASDに関する当事者研究の背景と目的
4-3 当事者研究と先行研究の統合から導かれる ASDに関する仮説
4-4 当事者研究から導かれた仮説の実証研究
第5章 回復と運動
5-1 情報環境・物理的環境への挑戦
5-2 人々の価値観や態度への挑戦
5-3 医学モデルに基づく臨床研究への挑戦
終章 当事者研究は常に生まれ続け,皆にひらかれている
謝辞
参考文献
注
索引
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ネギっ子gen
兵士O
またの名
ひつまぶし
Haruki
-

- 電子書籍
- リリア・プレグナント・ザ・ワールド・エ…
-

- 電子書籍
- 決定版 特捜戦隊デカレンジャー決戦超百科
-
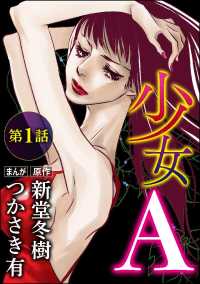
- 電子書籍
- 少女A(分冊版) 【第1話】
-

- 電子書籍
- なぜ、統計学が最強の学問なのか?(『統…
-

- 電子書籍
- 武士の本懐 - 名こそ惜しけれ




