内容説明
生活学の先駆者として生涯を貫いた著者最晩年の貴重な話――「塩の道」、「日本人と食べもの」、「暮らしの形と美」の3点を収録した。日本人の生きる姿を庶民の中に求め、村から村へと歩きつづけた著者の厖大な見聞と体験がここにはある。日本文化の基層にあるものは一色ではなく、いくつかの系譜を異にするものの複合と重なりである、という独自の史観が随所に読み取れる本書は、宮本民俗学の体系を知るための最良の手引きとなるだろう。
目次
1 塩の道
1.塩は神に祭られた例がない
2.製塩法とその器具の移り変わり
3.塩の生産量の増加に伴う暮らしの変化
4.塩の道を歩いた牛の話
5.塩を通して見られる生活の知恵
6.塩の通る道は先に通ずる重要な道
2 日本人と食べもの
1.民衆の手から手へ広がっていった作物
2.北方の文化を見直してみよう
3.稲作技術の広がり方
4.人間は食うためにだけ働いているのではない
5.食糧を自給するためのいろいろなくふう
3 暮らしの形と美
1.環境に適応する生活のためのデザイン
2.農具の使い方にみる日本人の性格
3.直線を巧みに利用した家の建て方
4.畳の発明で座る生活に
5.軟質文化が日本人を器用にした
6.生活を守る強さをもつ美
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
はっせー
142
宮本民俗学とも言われるほど1つの分野にした宮本さん。その晩年に書かれたのがこの本である。塩の道。文字通り海で作られた塩がどのように山の奥まで運ばれたのかを考察している。ここで面白いのは牛の話である。馬ではなく牛で塩を運んでいたのである。牛はどこでも寝れるし道に生えている草を食べてくれる。そこの話を聞いて道草を食うという言葉を思い出した。道草を食うは他のことに時間を費やすという意味である。牛は歩くのが遅くどこでも草を食べるのでもしかしたら語源は牛なのかもしれないと思った!また宮本さんの本を読みたい!2021/11/18
パトラッシュ
65
人は少しでも生活をよくしようと工夫する歴史を重ねてきた。その工夫の有様を、塩の獲得や衣食住の発展した経緯から跡付けている。豆腐を作るためニガリを含む悪い塩を買い、下り酒の空き樽を再利用して江戸で漬物が発達し、草鞋を編む生活が日本人を器用にしたなど机上の学問では決して明らかにされない指摘は膝を打つものばかりだ。晩年の講演をまとめた本だが、それだけに長年の研究成果を注ぎ込んで名もなき庶民が懸命に生きてきた姿を分かりやすく説く。歴史を民衆の努力という視点から見ることを教えてくれる、想像力を刺激してやまない本だ。2020/04/28
長澤まさみそっくりおじさん・寺
65
宮本常一は『土佐源氏』一篇しか読んだ事がなかった。本書は表題のものをはじめ『日本人と食べもの』『暮らしの形と美』の3本の講演集なので読み易い。昔の生産業の知らない世界は興味深いが「おや?」と思う事がしばしば。「なかろうか」「思います」「考えられます」等で締め括った想像が多い。今では否定される騎馬民族征服説を基準に話しているのは仕方ないとしても、戦国時代に戦う者と食糧生産者が分かれていたように言うが、兵は農民だった為に武将は農繁期には合戦を避けていたはずだが?。日本人の攻撃性の話も不確かである。2015/10/13
マエダ
55
塩というのは大事なものでありながら人々の認識が薄い。理由として塩そのものはエネルギーにならない為とのこと。循環の機能の助け、健康を保全する塩。塩で一冊書けるのは流石。。2023/06/15
i-miya
53
2014.02.08(02/08)(再読)宮本常一著。 02/06 (解説=田村善次郎) 宮本氏は日本の代表的な民俗学者の一人である。 その半面、一介の百姓であり続けた。 世間師。 本書、氏が最晩年に語ったもの。 未来社から著作集、刊行中(現在30巻)。 T12、16歳、父に、「親の元気なうちに他人の飯を食ってくるように」 祖父は優れた伝承者。 2014/02/09
-
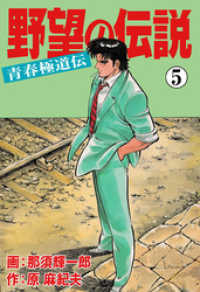
- 電子書籍
- 野望の伝説―青春極道伝― 5 マンガの…
-

- 電子書籍
- ビッグコミックスペリオール 2018年…




