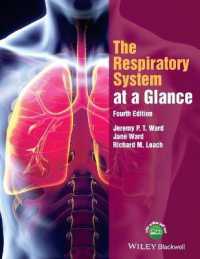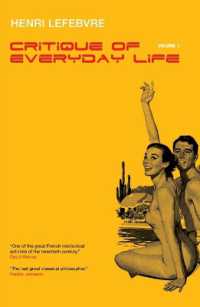内容説明
明智光秀の死後、光秀に関する史実を翻案した物語が、近世の京都を軸にして、どのように変容し受容され、また発信されたのか。現代日本人の思い描く光秀像にまで影響を及ぼす「伝承としての明智光秀」に迫るスリリングな史書。町・集団・家などが、書物や芝居などの情報と共振しながら、それぞれに多様な光秀像を創り発信する過程を実証的に明らかにする、本能寺の変の謎にも、「本当の」人物像にも迫らない、今までにない光秀論。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
58
武士道に反する謀反人ながら、光秀が江戸時代に高く評価され好意的な伝承も残っていたのは初耳だ。史実と無関係な創作も多いが、天下統一目前の信長を討った人物への関心が強かった証左か。当時はパワハラ上司な信長に対し光秀が謀反するものやむを得ずとの歴史観が形成され、それが『麒麟がくる』まで続いているようだ。本人や子孫が生きていたとの話を調べたり、小栗栖で討ち取った者について調べるなど関心のある人には興味深いが、明治以降は政府の考えひとつで評価が上下していた点は歴史を考える上で政治に引きずられぬよう留意すべきだろう。2021/02/25
ようはん
21
明智光秀は小栗栖で落武者狩りの農民に竹槍で突かれて死んだという最期が昔から自身に刷り込まれていたけど、それ自体は明確ではなく討ったとされる人物も江戸時代を通じて何度か変わったりと江戸時代の光秀に関しては興味深い内容は多かった。光秀のイメージの基礎も18世紀の明智軍記からの影響は大きいし実像はまだまだ謎に包まれてるんだろうな。2021/02/01
月をみるもの
11
タイトルだけ見て、てっきり天海説の話かと早合点してしまったが、豊臣政権を経て江戸時代〜現代にいたる光秀像がどのように形成されてきたかを調べる至極まっとうな本だった。光秀の生きた時代と現代をつなぐ500年の間に、初期の(出来事を記憶している人による)口承が、その後の文書にどのように影響を与え、その後の世相の変化が文書の受容をどう変化させたかが詳細に分析される。古事記が書かれた時代と、そこに記述されている最初の「歴史」の間も、ほぼ500年だが、その間は口承メインで文書は旧辞・帝紀くらいしかなかったのだよなあ。2020/09/21
オルレアンの聖たぬき
2
明智光秀は、前半生もわかってない、中盤から後半生はわかっているけれど、その後のことも全く……ということがわかった。なんなんだ?明智光秀って……と改めてわからなくなる新鮮な本です。2021/05/28
Hitomi Suganuma
1
光秀その人の実像ではなく人々がどうとらえていたかを解説している 明智憲三郎さんが こんな本が欲しかったこれがあれば楽に研究できたのに みたいな事いってたのが実感出来る2020/10/13
-

- 電子書籍
- 獣医師、アフリカの水をのむ 集英社文庫
-

- 電子書籍
- 配色デザインインスピレーションブックI…