内容説明
従来の品詞別、助動詞・助詞別の記述によらず、現代語文法の枠組みで古代日本語文法(古典文法)を解説した画期的文法書。五十音図をはじめとする基礎から、動詞、形容詞、述語の構造、時間表現、そして敬語まで、本書には、平安期を主とする古典文を読み解くための知識が網羅されている。また、文章読解にあたっては、文中における語の配列規則などを扱う構文論と、語形変化や語の構成を考察する形態論、この二つの視点を持つことが重要だと説く。広く日本語文法や日本古典文学に関心を寄せる人々に推奨したい一冊。
目次
はしがき
第1章 古代語文法の基礎知識
1・1 はじめに
1・2 五十音図
1・3 歴史的仮名遣い
1・4 文の基本構成
1・5 品詞
1・6 語の構造
第2章 動詞
2・1 動詞の活用
2・2 動詞の活用の種類
2・3 音便
2・4 動詞の自他
2・5 動詞の格支配
2・6 ヴォイス
2・6・1 受動態
2・6・2 可能態・自発態
2・6・3 使役態
2・7 補助動詞
2・8 代動詞・空所化
2・9 ダイクシス動詞
2・10 複合動詞
第3章 述語の構造
3・1 助動詞の分類
3・2 名詞述語文
3・3 肯定判断
3・4 否定判断
3・5 喚体句
第4章 時間表現
4・1 テンス・アスペクト
4・2 ツ形・ヌ形
4・3 リ形・タリ形
4・4 その他のアスペクト表現
4・5 キ形とケリ形
4・6 現在・未来
4・7 従属節のテンス
第5章 文の述べかた
5・1 法助動詞
5・2 証拠性
5・2・1 様相的推定・論理的推定
5・2・2 証拠に基づく推定
5・2・3 聴覚に基づく推定
5・2・4 視覚に基づく推定
5・3 推量
5・3・1 一般的推量・未実現の事態の推量
5・3・2 現在推量
5・3・3 過去推量
5・4 反実仮想
5・5 確述
5・6 当為
5・7 意志
5・8 勧誘・行為要求表現
5・8・1 誘い
5・8・2 勧め・行為要求表現
5・8・3 禁止
5・9 希望表現
5・9・1 願望表現
5・9・2 希求表現
5・10 疑問表現
5・10・1 真偽疑問文
5・10・2 補充疑問文
5・10・3 疑いの文
5・10・4 疑問を表さない疑問形式
5・11 文末付加要素
第6章 形容詞と連用修飾
6・1 形容詞
6・1・1 形容詞の活用
6・1・2 形容詞の特殊活用
6・1・3 形容詞の格支配
6・1・4 形容詞の並置
6・1・5 難易文
6・2 連用修飾
6・3 形容動詞
6・4 副詞
第7章 名詞句
7・1 連体修飾
7・1・1 内の関係の連体修飾
7・1・2 外の関係の連体修飾
7・1・3 連体修飾語の係りかた
7・1・4 形容詞移動
7・1・5 連体助詞による連体修飾
7・1・6 「の」と格助詞
7・2 準体句
7・2・1 形状性名詞句
7・2・2 作用性名詞句
7・3 格
7・3・1 主格
7・3・2 目的格・「を」格
7・3・3 「に」格・「にて」格
7・3・4 その他の格
7・3・5 複合辞
7・4 無助詞名詞
7・5 複数表示
7・5・1 名詞の並置
7・5・2 数量詞移動
7・6 代名詞
第8章 とりたて
8・1 副助詞
8・1・1 ばかり・のみ・まで
8・1・2 だに・すら・さへ
8・1・3 し・い
8・2 係助詞
8・2・1 主題
8・2・2 「も」
8・2・3 「ぞ・なむ・こそ」の生起位置
8・2・4 係り結びの特殊構文
8・2・5 「ぞ・なむ・こそ」の表現価値
8・2・6 係り結びの起源
8・2・7 「もぞ・もこそ」について
第9章 複文構造
9・1 条件表現
9・2 接続表現
9・3 接続助詞によらない接続表現
9・4 引用
9・5 挿入句
9・6 不十分終止
第10章 敬語法
10・1 敬語の分類
10・2 主語尊敬語
10・3 補語尊敬語
10・4 自卑敬語
10・5 自敬表現
文庫版補注
文庫版あとがき
出典一覧
参考文献
索引
-

- 電子書籍
- すれ違うままに【分冊】 7巻 ハーレク…
-
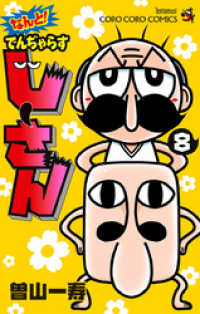
- 電子書籍
- なんと! でんぢゃらすじーさん(8) …
-
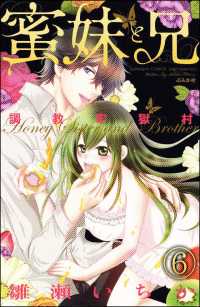
- 電子書籍
- 調教牢獄村(分冊版) 【第6話】 蜜妹…
-
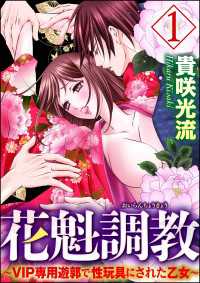
- 電子書籍
- 花魁調教~VIP専用遊郭で性玩具にされ…




