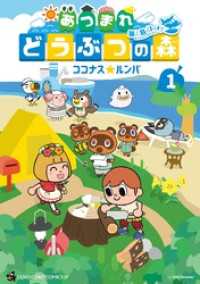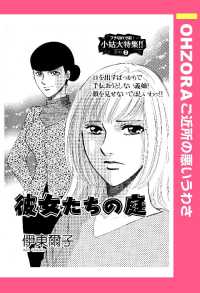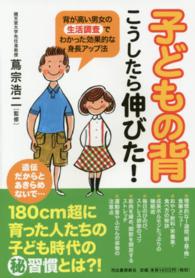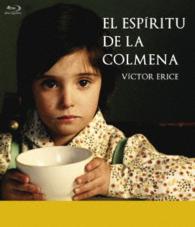内容説明
改憲論議、格差社会、日米関係、メディアと世論……いま議論になっている問題のはじまりは昭和にあった! 右や左の思想がはいりこみ、真実がみえにくい昭和史から最低限に知っておくべきことを一冊にまとめる。
目次
昭和の日本と今日の日本の類似点
時代状況の類似点
時間旅行のガイドブック
八つの観点
第一章 帝国憲法と日本国憲法のつながり
昭和史の断絶と連続
天皇主権の下でも天皇の責任は問われない
藩閥政府と元老
帝国憲法下でなぜ政党政治は可能になったのか?
立憲君主国=日本
政党内閣制の確立
帝国憲法でも平和とデモクラシーは実現できるか?
幣原とマッカーサーの利害の一致
日本国憲法は「押しつけ憲法」なのか?
戦争放棄
過去は清算できたのか?
憲法第九条があったから平和だったのか?
第二章 政党政治をめぐる三つの疑問
なぜ戦前昭和の政党政治は存在感がないのか?
政党政治研究が立てた三つの問い
世界的なデモクラシーの潮流
政党が担う政治へ
戦前昭和の二大政党は相互に似ている
二大政党制の限界
政党内閣復活の可能性はあったのか?
大政翼賛会がもたらしたもの
占領下の政党
独立回復に吹く追い風
独立回復後の政党のねじれ
一九五五年体制の成立
戦前回帰を不安視する国民
政治の季節から経済の季節へ
自民党一党優位体制の変容
機能不全に陥る政党政治
第三章 戦前と戦後に共通する協調外交
戦前昭和の協調外交とは何か?
政党内閣の中国政策
追い詰められた軍部が打った手
なぜ国際連盟から脱退したのか?
広田外交が先か現地軍が先か
国民にとってなじみの薄いドイツとの協定
経済的な後ろ盾のアメリカとの外交関係の変化
日独伊三国同盟
独ソ戦がきっかけに
対米協調外交の復活
戦前と変わらない外交方針
国家的な独立の回復
先進国日本のアメリカからの自立
対米協調から多国先進国協調へ
第四章 安全保障政策
軍縮に進む戦前日本
当てがはずれ見込みちがいもあった現地軍
合理性を欠く海軍の判断
日中戦争をめぐる戦略論の対立
基本戦略の不統一
組織利益の対立が破局をもたらす
日米安保条約と平和憲法の矛盾
なぜ不平等な日米安保条約を結んだのか?
なぜ不平等な日米安保条約を受け入れたのか?
沖縄返還をめぐって
改憲に向かわない「非核専守防衛国家」
斬新なソフトパワー路線
新冷戦下の日本の安全保障政策
第五章 格差の拡大から縮小へ
格差拡大社会=日本
大戦景気と昭和恐慌のギャップ
失言から始まった金融恐慌
期待に応える高橋(是清)蔵相
「下級国民」の選択
再び危機から日本を救う高橋是清
日中戦争下の経済格差の是正
焼跡の闇市
占領権力による〈上〉からの改革
終身雇用と年功賃金の誕生
農村生活の現実
高度経済成長の光と影
国民の希望としてのオリンピックと万博
再び格差拡大へ
第六章 絶え間なく起きる昭和の社会運動
さまざまな社会運動が起きていた
大衆は社会主義運動に何を求めたのか?
人々に支持された五・一五事件
人々に支持されなかった二・二六事件
〈上〉からの国民精神総動員運動とは?
新体制運動も挫折する
社会主義運動の再起動
女性の署名活動から始まった原水爆禁止運動
安保反対運動はなぜ大規模化したのか?
戦後もあった〈上〉からの運動
最後の大規模な社会運動
国民が本当に求めていたのは何か?
第七章 文化が大衆のものになる
昭和のはじめにデパートの出店ラッシュ
高嶺の花だったラジオ
どんな映画が流行したのか?
日中文化交流の萌芽
失われた中国再認識の機会
流行歌は禁止、ジャズは容認
文化の政治利用
渇望される活字文化
アメリカ文化の影響
戦後日本映画の復興
活字文化からテレビ文化へ
週刊誌の創刊ラッシュ
豊かな生活への憧れとバブル文化
第八章 メディアをめぐる問題の起源
権力・メディア・世論
売れるためならば社説も変える
新聞の大衆化路線
広報外交の逆効果
中間層から始まるメディア統制
戦争に倦む国民
大本営発表対宣伝ビラ
戦前と戦後の検閲のちがい
アメリカによるラジオ番組「真相箱」
テレビと映画への作家の起用
佐藤(栄作)首相の引退記者会見
外務省機密文書漏洩事件
メディアと政治をめぐる三つの論点
メディアと政治の「共犯」関係
昭和末年の自粛ムード
参考文献
あとがき
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Aya Murakami
かんがく
月をみるもの
keint
バルジ