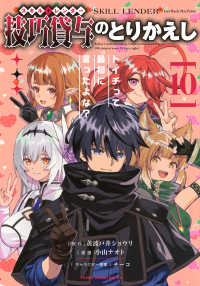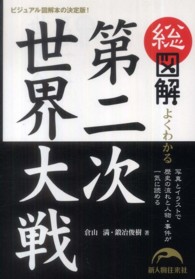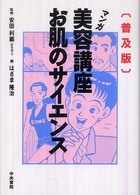- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
コロナ、AI、異常気象……
押し寄せる変化を「編集力」で味方につける!
「編集」という言葉から、何を思い浮かべるでしょうか?
雑誌・書籍の編集や映像の編集のような、何かしらのメディア情報を取り扱う職業的な技能をイメージされるかもしれません。
ここでは、「編集」という言葉をうんと広い意味で捉えます。
そもそもわたしたちは、ありとあらゆる「情報」に囲まれて生活しています。
起きた時の体の感じ、外の天気、出かけるまでの持ち時間、テレビから流れるニュース、朝食のメニュー、クローゼットの服と今日のコーディネート、
いずれも「情報」であり、そういった雑多な情報をのべつ幕なしに「編集」しながら生きています。
ここで言う「編集」とは、こうした「情報」に関わるあらゆる営みのことを指すものです。
本書で考える「編集力」は、明日の仕事や暮らしに役立つ技能、という範囲にとどまるものではありません。
この世界のいたるところにある編集の営みを思い、新たなものの見方やそこにある方法を発見していくことを通して、ひとりひとりの中に思い思いに引き出されていくまだ見ぬ潜在力こそが、本書で取り扱いたい編集力です。
生命活動のOS(オペレーションシステム)とも言える広義の「編集力」を、「方法」として工学的に読み解くことで、人間が携えるべき基本的な能力の仕組みを明らかにし、改めて装填し直していく。
「編集」を「工学」することによって、あるいは「工学」を「編集」することをもってして、相互作用する複雑な世界の中で、人間に本来備わる力が生き生きと立ち上がっていくことを、「編集工学」は目指しています。
そして、この「人間に本来備わる力」というのは、その現れ方がひとそれぞれに違うはずです。おそらくこれを、「才能」というのだと思います。
才能の「才」は、古くは「ざえ」とも読み、石や木などの素材に備わる資質のことを言いました。それを引き出すはたらきが「能」です。
「才」は素材の側にあり、「能」は職人の腕にある。才能とは、引き出す側と引き出される側の相互作用の中にあらわれてくるものであるようです。
内側にある「才」をいかに引き出せるか。自分個人だけでなく、他者の「才」やチームの「才」、場の「才」ということもあるでしょう。
素材の内側と外側を自由に行き来する「能」としての、しなやかな編集力が必要です。
自分の内側に眠る「才」の声を聞き取り、編集力という「能」をもって表にあらわす。そこに関与するさまざまな方法をエンジニアリングしたものが、「編集工学」であるとも言えます。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
けんとまん1007
Tenouji
江口 浩平@教育委員会
チャー
P.N.平日友
-
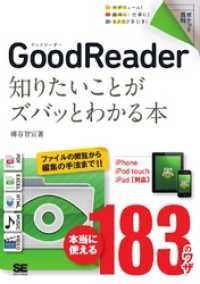
- 電子書籍
- ポケット百科 GoodReader 知…