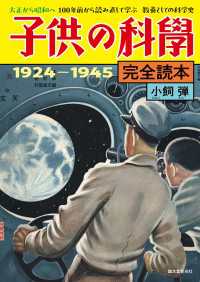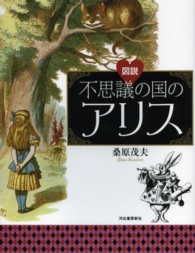- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
「無数にある日本の季節祭のなかにとけこんで、目や耳で自国を知ろうとする人のために、本書はささやかな友人になれたらと思うのである」12か月の祭礼を民俗写真の第一人者が興奮の旅の記録とともに綴る。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
HANA
69
新年を寿ぐ傀儡師や春の野を行く遍路、鎮花祭に早乙女、盆に秋祭りと日本の四季を彩る数々の祭り。そんな数々の祭りを写真と文で解説した一冊。撮影されたのは六十年代、五十年昔だけど、今思えばその頃がこういう祭りを写す最後のチャンスだったのかも知れないなあ。近くを見れば傀儡師は姿を消し、遍路もバスツアーに姿を変えているし。季節も地方も全てが平均化され消費されるような現在から見れば、ノスタルジアかもしれないけどこういう芸能と信仰と娯楽が混然一体となった姿は羨ましくも感じるなあ。当時の空気さえ切り取った良い一冊でした。2021/03/21
ワッピー
33
写真家・芳賀氏のニッポンの祭歳時記。昭和30年代、日本が高度成長期に入って社会構造の変化が伝統のある祭にも大きく影響を及ぼしていることが幾度も言及され、伝統を継承することの難しさ、担い手の意識の変遷が読み取れます。しかし、それでも写真に写る変化の兆しと伝統との奇妙なバランスが見えて、現代視点からは共に遠くなってしまった古い風景が懐かしく、また新しくも感じられます。京都の鎮花祭の章に写った洛北の風景は今も在るのだろうか?記録された祭の手順は今も踏襲されているのだろうか?少し前の日本の旅を堪能しました。2022/02/23
たまきら
24
1960年代に撮影された貴重な写真から見えてくるのは、日本各地が持つコミュニティの力だ。独自の文化を伝承することができる確かな知識と密な人間関係。その独特な世界をあっけらかんとのぞきこむ写真は無邪気で、ほどよく距離感があり、また程よく親近感がある。どきどきした。もっとこの人の記録が見たい。2020/10/22
紫羊
18
書店で平積みされた表紙を見て即買いした。写真も文章も素晴らしい。昭和の中頃までの日本は、もはや書物の中にしかないことを再確認した。その頃を微かにでも記憶している身としては、懐かしさより無常感が勝った。2021/08/15
MO
7
著者の写真がいいな、と思って手にとった。恐らく折口信雄の世界を写真記録したものだろうと当たりをつけた。掲載の祭りは高度経済成長期に入っているので、土地の精神性と切り離されて観光客用となっている。消えゆく地方の土着信仰を残そう、という思いもなく、既に取り返しのつかないところまで行っているのを受け入れている感じ。土着の時代と精神性を瓦解された現代との狭間の記録と思うと、これはこれで興味深い。文章は中途半端な説明と感想が入り乱れているので祭のイメージに入りこむことができなかった。惜しい。2022/06/14