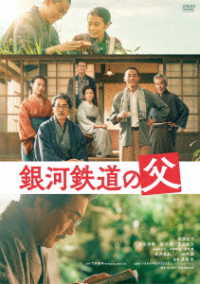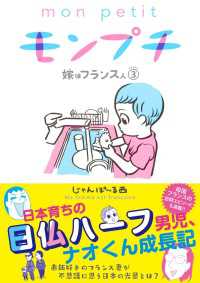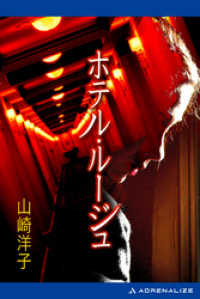- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
韓国人元徴用工問題を解決済とする日本政府。一方で元徴用工が補償を求める個人請求権が存在することも認めている。彼らの訴えに耳を傾けることが、戦後七十五年間、民間人の空襲被害や外国籍の人々への戦後補償を放置してきた日本社会に問われているのではないか。著者は弁護士として中国人強制労働事件の和解交渉にかかわった経験を踏まえ、元徴用工問題和解への道を探る。
目次
はじめに
第1部 「徴用工問題」と日韓関係のゆくえ
第1章 韓国大法院判決が投げかけた問題点
植民地支配の清算は含まれず
日本の日韓条約反対運動にも欠落していたもの
「八項目要求」中に、元徴用工問題も入っていた?
個人の請求権は放棄されていない
外交保護権の放棄論とは?
日本の最高裁も個人の請求権は失われていないという見解
条約、協定で個人の請求権を消滅させることが出来るのか
第2章 植民地支配の実態に向き合う
韓国併合の歴史
植民地支配はよいことをした?
韓国叩き
負の歴史に向き合う勇気
第2部 中国人強制連行・強制労働
第1章 中国人強制連行・強制労働の歴史から学ぶ
閣議決定「華人労務者内地移入に関する件」
「花岡事件」──一九四五年六月三〇日の「暴動」
俘虜収容所長からの報告
秋田地方裁判所の判決
シンプソン報告書と横浜BC級裁判
東京裁判(第二次)での戦犯訴追を免れた岸信介
南方戦線にも強制連行された中国人
「幻」の外務省報告書
国から企業への不可解な補償
第2章 中国人受難者・遺族による損害賠償請求
鹿島建設との交渉開始
「共同発表」で責任を認める
提訴から和解の成立まで
大きな反響を呼ぶ
地元大館での追悼行事開催
新村正人元裁判長の献花
花岡事件祈念館の開設
第3章 全国で相次いだ損害賠償請求訴訟
「法律の壁」「条約の壁」
劉連仁事件──一三年間の逃亡・潜伏生活からの救出
損害賠償に応ずることは「条理」に適う
第4章 西松建設(旧西松組)広島安野の裁判、和解へ
地裁で棄却、高裁では勝訴判決
最高裁で再び棄却に
判決末尾で述べられた「付言」
加害の事実を認め、歴史的責任を認識し、深甚なる謝罪
基本原則を踏まえた和解
チャンスを生かすことができたのは持続した運動があったから
その後の和解事業の展開
鈴木敏之・元広島高裁裁判長からの書簡
日中国交正常化四〇周年の光景
鈴木敏之・元広島高裁裁判長による献花
安芸太田町長の挨拶
第5章 三菱マテリアル(旧三菱鉱業)も和解へ
過ちて改めざる、これ過ち
花岡、西松和解の延長上の和解
交渉→裁判→交渉の経緯をたどる
花岡、西松をはるかに超えた和解が実現
三菱マテリアル和解が拓く展望
平和資源として活かそう
新聞、テレビ等メディアの評価
第6章 判決の「付言」に見る裁判官たちの苦悩
「付言」の系譜をたどる
「付言」の活用を訴えた東郷和彦氏
「付言」を書いた裁判官の心情
第3部 問題解決には何が必要か
第1章 日韓基本条約・請求権協定の修正、補完は不可避
日韓基本条約・請求権協定と日中共同声明との違い
日韓基本条約・請求権協定を修正・補完した日韓共同宣言
平壌宣言との比較
自民党、社会党、朝鮮労働党による三党合意(共同宣言)
「解決済み」論は通用しない
日韓基本条約・請求権協定の修正・補完
元徴用工・遺族に対する賠償がなされている事例
六五年日韓基本条約・請求権協定への「先祖返り」
第2章 戦争被害における個人請求権
総力戦下拡大する戦争被害
空襲被害者による賠償請求
原爆被害者による賠償請求
強制連行・強制労働としてのシベリア抑留
慰安婦問題に見る強制性
第3章 冷戦によって封印された個人賠償の復権
戦争賠償「放棄の経緯」には何があったか?
ドイツ型基金による解決に学ぶ
第4章 韓国憲法と日本国憲法
韓国憲法前文
未完の日本国憲法を補完する
独・仏の和解に倣う
第5章 負の歴史に向き合う
花岡和解から二〇年、変わらない日本政府見解
なぜ、負の説明を回避するのか
第6章 日韓の関係改善を求めて
声明「韓国は敵なのか」署名運動
言論労組の活動
安倍政権の朝鮮半島政策の転換を求める声明
日韓法律家共同宣言
終章 あとがきに代えて
『反日種族主義』を読んで
「韓国の つき文化」?
大法院判決は の裁判?
強制動員、賃金差別の虚構性?
二枚の間違った写真で全てが否定されるか
もともと請求するものなどなかった?
あとがきに代えて
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Porco
たぬきのしっぽ
吉田よしこ