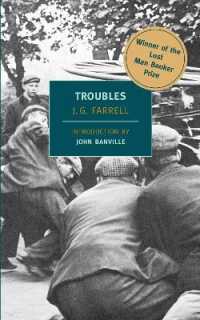内容説明
※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
うちの子、頭はいいんだけどテストや成績はイマイチ。そう、「頭がいい」と「勉強ができる」は違う! と、前作『学力テストで測れない非認知能力が子どもを伸ばす』ではポジティブに解き明かされた。「知識のインプット(認知能力)」」だけに収まらない「非認知能力」が教育改革と共に変わる大学入試や教育現場、来たるAIとの共存・共働する新しい時代に必要と言われている。また、勉強だけできても、先が見えず何が起きるかわからない時代を生きることは難しいと実感する今、求められるのは、「正解」ではなく「最適解」を見出す力だ、これも非認知能力である。
この「非認知能力」、子どもだけが伸ばせるものと誤解されがちだが、実は大人になってからも伸ばすことができる。本書は、教育・保育・子育てにかかわる方々をはじめ、ビジネスの世界で人材育成に携わっている方々にも、その力の伸ばし方を理解し参考にできる一冊である。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ムーミン
18
コロナに振り回されている現在の状況こそ教育のスタンスを見直すチャンス。この状況をどう受け止め、子どもたちも先生も地域の大人も成長するか、パワーアップするか。昨年から取り組み始めている研究の中で、参考になるものがほしいと思っていた具体案が提示されていて、ありがたく思いました。2020/07/02
かずぼん
6
コロナ禍の中で出された本である。もちろん、感染が拡大する以前から、前著の具体化版として企画され書かれてはいたのだろう。点数化できる認知能力と、点数なできない非認知能力とを区別し、どちらか一方を重視するのではなく、両者をともに高めていければ一番良い。しかし、非認知能力についてはまだまだ開発途上な面があり、その具体化と検証がしばらくは必要である。本書もそういう前提で書かれているが、ともすると、非認知能力さえ身につければよし、となりかねない点は留意したい。昼間の学校があって、放課後の学童があり、どちらも大切だ。2020/08/14
Go Extreme
2
認知能力:記憶・理解・判断 OECDの社会情動的スキル・認知的スキル 非認知能力:3レベル⇒プラス・マイナス面あり 3つのレンズ:自分と向き合う・自分を高める・他者とつながる フィードバック・意識づけ⇒行動強化 振り返り・リフレクション→メタ認知 相互主体的な学び PBL・課題解決型学習:パーソナル→グループ→ソーシャルプロジェクト 体験→経験→学び→多様な能力 AARサイクル:見通し→行動→振り返り ハイリスク業務のノンテクニカルスキル EBPM:エビデンス・ベースト・ポリシー・マイキング 正解<納得解2020/07/25
hara_haru
1
前著と比べると一気に専門的になったが、漠然としていた非認知能力とその育成の仕方について理解できた。昔から授業力のある先生って、このギミックの使い方に長けてたんだな。2021/12/20
ぷりん
1
非認知能力の伸ばし方…というよりは、非認知能力につながる価値ある行動の気づかせ方かな? 読んでいると、実は今までも当たり前のように行っていたことばかり。主体的・協働的に取り組めるように意図して教材や活動を選択していたこと、学び方を振り返らせていたこと、行動を価値づける声かけをしてきたこと…。日々の取り組みの意図や子供の活動状況に対する言葉がけについて、もっともっと意識していこうと思う。2021/06/20