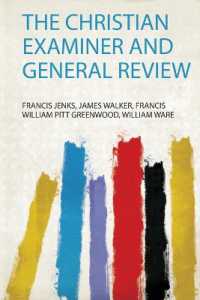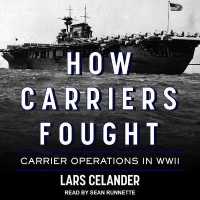- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
「うちは、レールものを買わへん」という祖母の台所哲学によって味感を育まれた著者。いまも“ほんまもん”を求めて「京を食う日々」を暮らす。春には掘りたての筍、夏には鮎や鱧、秋から冬には京野菜の鍋と漬物、さらに豆腐や湯葉や生麩、そして、鮒ずし、鯖ずし、「へしこ」といった発酵食品に舌つづみをうつ。かしこまった京料理におさまらない著者の食欲は、真摯で求道的でさえある。「かつて日本は貧しかったが、食材への気配りは京都だけでなく全国どこの家庭にもあった」と懐かしむ。植物染を専らとし、日本の伝統色と染織史の研究家でもある著者は「料理も染色も基本は同じ」と語る。すなわち「素材を見極める」「時間を見計らって火の強弱を気遣う」という点が同じだという。そして、染色も料理も「早く済ませたいと、どこかで手抜きをすると必ず失敗する」という。垂涎のエッセイ集である。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
さっちも
10
著者は料理人でもなく、主婦でもないので料理や素材に対する見識が浅い。京都人を自任するわりに向島にお住まいなのは、なんだかなーとモヤモヤする。あえて偏見を言わせて貰えば、京都は鬱屈した田舎であって、田舎であるのに様々な権威が存在する。 そのしがらみと世間体のなかで生きる京都人の持つしたたかさや、頑なさ、保守的、処世術、価値観が魅力だけれども、それが本書にはない。取り上げるトピックが面白そうで買ったけれどイズムが感じられない。ウンチクが多い2021/12/04
B.J.
8
●昔、蘇民将来という人物が備後国にいた。スサナオノミコトが旅をしているとき、一夜の宿を借りようとした。初めは裕福な巨旦(こたん)将来という家にいったが断られた。ところが隣に住む、家は貧しいけれど心が美しい兄の蘇民将来は迎え入れて、粟飯などをごちそうした。そこでスサナオノミコトはそのお礼にと、茅の輪に「蘇民将来の子孫也」と書いて、腰につけていれば疫病を免れると告げた。 ⇒祇園祭りは京都の人々の疫病退散を祈ることで始まった。その祭神である祇園八坂神社はスサナオノミコトを祭っている社である。・・・本文より2020/03/02
しいら
3
内容もさることながら、美しい日本語を感じる本だった。2014/07/23
love_child_kyoto
2
深いグルメ本2010/08/29
-
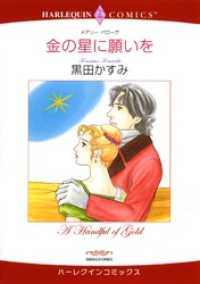
- 電子書籍
- 金の星に願いを【分冊】 5巻 ハーレク…
-
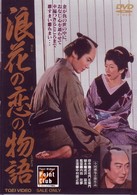
- DVD
- 浪花の恋の物語