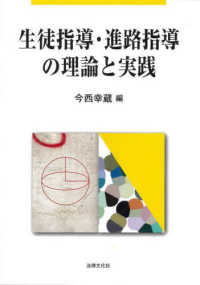内容説明
科学出版賞受賞作家の書き下ろし最新作
「全生物に読んでほしい!」人気YouTuber・ヨビノリたくみ氏絶賛
いま、生物学の分野で静かな革命が進行しつつある、と言ったら読者の皆さんは驚くだろうか? その生物学の分野とは、ゲノム科学である。ゲノム科学に関する新しい知見がネットに流れない日の方が珍しい。
「寿命を伸ばす遺伝子発見!」
「『がんゲノム医療』検査に保険適用」
なんだがすごいことがこの分野で起きているっぽい。だが、なぜ、「突然」こんなことになっているのか? その疑問に答えてくれる報道は少ない気がする。本書の目的はそれを少しでもわかりやすく説明することにある。
そのために、本書ではDIGIOMEという造語を導入した。DIGIOMEとは何か? それは、デジタル信号処理系としてゲノムを捉える考え方だ。ゲノムを構成するDNAが、ゲノム情報という意味で、われわれ生命の設計図たる情報を担っていることは、ワトソン=クリックによるDNAの二重螺旋構造の発見の頃から知られていた。だが、本書ではそこを一歩踏み込んで、ゲノム自体をデジタル情報処理装置として捉える見方を提案したい。
我々人類が、デジタル情報処理装置の恩恵を日常的に享受できるなったのは、わずかにここ数十年のことに過ぎない。だが、生命体はそのそもそもの誕生時からこの高度なディジタル情報処理系の恩恵を享受してきた。周知の様に、我々人類がデジタル情報処理装置の恩恵を享受するには、高性能ながら安価な情報処理装置(例えば、スマホ)の発明が必須だった。生命体はそのような精密な情報処理装置を持っていないにも関わらず、ゲノムをデジタル情報処理装置として機能させることに成功してきた。本書で語りたいのは、なぜ、そんな奇跡のようなことが可能だったのか、ということだ。
実際、デジタル信号処理系たるゲノムは、われわれ人類が作り上げた精緻で緻密なそれとは、にて非なる側面をもっている。ある面では我々のそれより優れているし、ある意味では劣っている。そして、いま、このタイミングでその詳細が詳らかになったのは、デジタル信号処理系としてゲノムの動作を克明に観測して記録できるだけの技術と知識を我々が手にしたことによる。いままで秘密のベールの奥に隠されていたその機構の謎が日々、その観測技術によって続々と白日のもとにさらされている。前述のゲノム科学における新発見の連鎖はその帰結に過ぎない。そして、その技術の一端にはいま流行っているAI=機械学習の進歩も大きく関わっている。この本はそんな存在、DIGIOMEを巡る冒険譚を、極力最先端の知見を用いて語ることを目的とする。この本を読み終えた時、きっとあなたは、いままで見ていた「生命」をそれまでとは随分と違う目で見ることができるに違いない、と信じる。
目次
第1章 ゲノムー38億年前に誕生した驚異のデジタル生命分子
第2章 RNAのすべて(トランスクリプトーム)ータンパク質にならない核酸分子のミステリー
第3章 タンパクのすべて(プロテオーム)ー組成を変えずに性質を変える魔法のツール
第4章 代謝物のすべて(メタボローム)ー見過ごされていた重要因子
第5章 マルチオミックス 立ちはだかるゲノムの暗黒大陸
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
mae.dat
evifrei
minochan
Bartleby
-

- 洋書電子書籍
- Operation Just Caus…
-
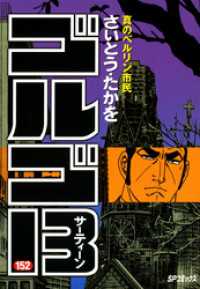
- 電子書籍
- ゴルゴ13(152)