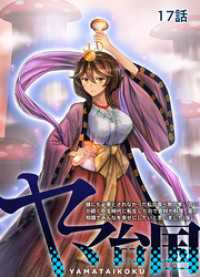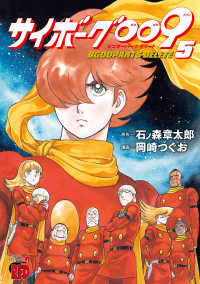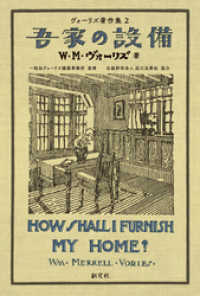内容説明
ホモ・サピエンス(現生人類)の出アフリカ状況、ネアンデルタール人との接触、デニソワ人の発見、ゲノム解析等、この5年で研究状況は様変わりした。最前線の研究者らはどんな視点で人類の拡散を解明しようとしているのか。わかりやすく説く。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
yamatoshiuruhashi
42
人類はどうやって世界中へ広がったか。6人の執筆者による7つの章立て。それぞれの論文の繋がりを日本人としてタイトルづけるとすればこの表題になるのだろうが、実は人類の交代と発展の文化的な考察だとおもう。随所に数式やグラフが出てくるがその考え方の基礎も丁寧に説明されており、理論値そのものは理解できなくても思考過程、推察の理由は理解できる。本書においてはネアンデルタール人と現代人が交雑したこと既に確認された事実とされている学会の研究速度に驚いた。2021/03/09
katsubek
18
かなり学術的な書。全部を理解するには専門知識を要求する書である。そんなわけで、面白いと思うところを読んでみました。高校で学んだころとは、全く異なるではありませんか。ネアンデルタール人以外の旧人の話、現代人の中に息づいている旧人の遺伝子。新しいことを知るのが、こんなに楽しいとは! 門外漢でも、きっと楽しめます。2020/04/17
takeapple
13
なぜ、どうやって我々ホモサピエンスは世界中に広がったのか。そもそも人類はどこでどのように進化してきたのか、研究が進んだ今でも大いなる謎である。私が大学で考古学を専攻していた30数年前と比べると分かったこと、定説となっていることは大きく違っている。でもまだ中学校の歴史の資料集などには、30数年前から変わっていない今では覆された記述もある。良く整理していかないとなあ。もしかしてアジアに最初に来たホモサピエンスは、デニソア人やホモフローレシエンシスと共存していたなんて言うことが事実なら何とワクワクすることか。2020/05/04
はちめ
13
この分野は発掘の進展やDNA分析の進捗により新たな知見がすごい勢いで加わっているが、逆にその事が事実を複雑にしているようだ。グレイトジャーニーがイメージさせるようなロマンチックな現実はなく、アフリカを出た現生人類はそれぞれの自然環境に順応しつつ、既に先住者としてあった旧人と交雑も含め渡り合わなければならなかった。特にデニソワ人の与えた衝撃は大きい。今後さらなる研究の進展が待たれる。☆☆☆☆★2020/02/22
hal
9
西秋先生が代表の『パレオアジア・プロジェクト』に参加しておられる先生方による、最新の研究成果のようです。昨年成功なさった実験航海プロジェクトの海部先生の講演会を元にした章もあります。DNAに関しては、難しすぎて私には完全に理解できないのですが、科学捜査みたいで興味深いです。ネアンデルタール人は現生人類に出会う前から人数が減って近親婚が進んでいて、現生人類の非アフリカ人もボトムネックだったので人数は少なく、交雑することで現生人類は生き延びられたのだろうか。さらなる研究の進展を期待します。2020/03/13