- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
江戸時代から続く「小売の王様」は、その使命を終えたのか?
三越、伊勢丹、高島屋、松坂屋、大丸、西武、東急、阪急……
変革はいつ止まったのか、再び革新は起こるのか。
江戸時代の呉服屋に起源を持ち、およそ四〇〇年の歴史を誇る百貨店。近代小売業の先駆、業界のトップとして、日本の消費文化を創ってきた。しかし、いまや経営は厳しさを増す一方で、その存在が揺らいできている。三越、伊勢丹、高島屋、松坂屋、大丸、西武、東急、阪急……。かつて隆盛を極めた百貨店は、商品販売で、宣伝戦略で、豪華施設で、文化催事で、いかにして日本社会を牽引してきたのか。「モノが売れない」時代となり、デジタル化が進む現代において、何を武器に活路を拓くのか。「週刊東洋経済」副編集長が、その歴史と展望に迫る。
【目次】
はじめに
序 章 「イノベーター」として君臨した百貨店
第一章 商い――「モノ」が売れない時代に何を売るか
第二章 流行創出――文化の発信地にまだブランド力はあるか
第三章 サービス――「おもてなし」は武器であり続けるか
終 章 かつての「小売の王様」はどこへ向かうのか
おわりに
主な参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
nishiyan
10
「商い」、「流行創出」、「サービス」を切り口にラストは「小売の王様」として君臨した百貨店・デパートの歴史と今後を追った新書。百貨店のそもそもの起こりから現代までの流れを小ネタを挟んで解説している。興味深かったのは越後屋呉服店の丁稚奉公から始まり、女性の社会進出、通信販売などにまで言及した百貨店のサービスについて掘り下げた章。百貨店の蓄積してきたデータが今後、新しい技術と交わったときにどんな化学反応を起こすのか気になるところ。暗い話題ばかりの百貨店業界だが、少しだけ光明が指しているように感じた。2020/06/02
史
5
コロナ禍直前に刊行された本。というのがどこか惜しい。しかしながら明治時代から21世紀直前まで世の中の華として扱われていた百貨店の栄枯盛衰をまんべんなく語り尽くしております、屋上遊園地、懐かしいですね。格差社会がさらに広がっている昨今、おそらく形は違えどもまだまだ完全になくなるようなことがないんだろうなと思わせるのは、やはりその歴史の長さかな。新書であれども中々味わい深いものがあります。2025/03/09
nadaha
3
百貨店は日本の小売業の歴史において最初の王様だった。あらゆる量販店は百貨店の築いてきた歴史の上に立っている。今でも元気のある百貨店は数えるほどしかなく、苦境に喘ぐ業態だけどもワクワクする買い物体験や良いものが並ぶ空間、需要を喚起する店にはロマンがある。百貨店法による出店規制、不景気とファストファッション、通販の台頭など逆風を跳ね返すことが出来るのか。好景気になればまた豪華主義な時代が来るような気もするが、景気が回復することなんかあるのだろうか…。2025/03/03
Kazuo Ebihara
3
子供の頃の憧れの場所、デパート。 屋上で遊び、買い物をし、 大食堂で食事をとることは、 家族にとって一大行事だった。 そんな百貨店の江戸時代から今日までの 変革の歴史を解説。 販売手法、宣伝のイノベーター。 豪華で最新設備を完備した巨大な建造物。 文化、流行の発信地。 夢を形にし、日本人の消費生活をリードして来た 東西の百貨店の栄枯盛衰記。 今は、ちょっと辛いね。 頑張れ、百貨店。2021/02/28
しまうま
3
東洋経済の業界特集記事を読んでるような感じ.部外者は軽い読み物として楽しめるが,当該業界の人からすると参考になることもないだろう,というような.新書だからそれで良しか.現在の各社の取り組みに対しては取材協力もらってるからか全く批判的な目線なし.2020/09/26
-
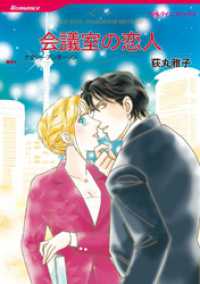
- 電子書籍
- 会議室の恋人【分冊】 1巻 ハーレクイ…
-
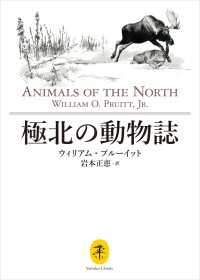
- 電子書籍
- ヤマケイ文庫 極北の動物誌 山と溪谷社
-

- 電子書籍
- こわれかけた愛【分冊】 10巻 ハーレ…
-
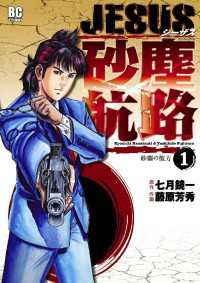
- 電子書籍
- JESUS 砂塵航路(1) デジコレ





